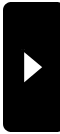2009年02月25日
2009年02月24日
(京)驚天動地(きょうてんどうち)
驚天動地(きょうてんどうち):
世間を大いに驚かせ,人々をあっと言わせること。
天を驚かし地を動かす意から。出典:白居易,李白墓
(新明解故事ことわざ辞典)
故事成語いろは集は,今日で一応の上がりである。
一応というのは,語源解釈の仮説,あいまいさを残したままであるからだ。
よって今後は,宿題として次の点を解明していこうと思う。
壟断(ろうだん):
(岡の断ち切ったようにそびえたところ,ではなく)盛り土の上でさばくこと
辟易(へきえき):
(おどろきたじろぐこと,ではなく)易きを辟ける(=天命のなかで旧恩に応える)
東奔西走(とうほんせいそう):
(出典不明)南船北馬との対比で何かを走らせているその走り方
魑魅魍魎(ちみもうりょう):
(魑魅と魍魎,ではなくて)山と川で生まれる精霊の一語
跳梁跋扈(ちょうりょうばっこ):
(出典不明)梁を跳(と)びこし扈を跋(ふ)みつぶす(梁,扈は地名)
綸言汗の如し(りんげんあせのごとし):
綸言は(汗のように広がりもどせない,ではなく)基本であって実用を加えていく
濡れ衣(ぬれぎぬ):
(無実の罪を受ける,のではなく)罪を避けるために自ら被るもの
類を以て集まる×類を以て集める○
(似ているものは集まるのではなく)似ているものは同じ卦に集める
温故知新(おんこちしん):
(故きをたずねる,のではなく)死んだ何かを温めると発見がある
大同小異(だいどうしょうい):
(だいたいおなじ,ではなく)方法は一つでも結果は見方によって異なる
年年歳歳,歳々年々(ねんねんさいさい,さいさいねんねん):
1年の命の花は代りながら変らず,人は歳を重ね代らずに変る。
付和雷同×不和雷同○(ふわらいどう):
和せず人前で大声をだす
烏合の衆(うごうのしゅう):
(カラスのように統制も規律もない群衆,ではなく)項羽に合した戦闘集団
漱石枕流(そうせきちんりゅう):
礼による身分制度そのものを否定する完全な自由
嚢中の錐(のうちゅうのきり):
(才能は隠れていても現れる,ではなく)狭い場所では能力を発揮できない
満を持す(まんをじす):
(弓をひきしぼる,のではなく)徳が満ちるまでの時間を待つ
荒唐無稽(こうとうむけい):
(荒唐+無稽ではなく)荒れた唐には祭礼の酒器もない
遠慮なければ近憂あり(えんりょなければきんゆうあり):
時間ではなく距離の問題
驚天動地の新発見を楽しみにしている。
ここまで毎日書き続けられたのは,多くの人の支えがあったからだと思う。
心より感謝する。
世間を大いに驚かせ,人々をあっと言わせること。
天を驚かし地を動かす意から。出典:白居易,李白墓
(新明解故事ことわざ辞典)
故事成語いろは集は,今日で一応の上がりである。
一応というのは,語源解釈の仮説,あいまいさを残したままであるからだ。
よって今後は,宿題として次の点を解明していこうと思う。
壟断(ろうだん):
(岡の断ち切ったようにそびえたところ,ではなく)盛り土の上でさばくこと
辟易(へきえき):
(おどろきたじろぐこと,ではなく)易きを辟ける(=天命のなかで旧恩に応える)
東奔西走(とうほんせいそう):
(出典不明)南船北馬との対比で何かを走らせているその走り方
魑魅魍魎(ちみもうりょう):
(魑魅と魍魎,ではなくて)山と川で生まれる精霊の一語
跳梁跋扈(ちょうりょうばっこ):
(出典不明)梁を跳(と)びこし扈を跋(ふ)みつぶす(梁,扈は地名)
綸言汗の如し(りんげんあせのごとし):
綸言は(汗のように広がりもどせない,ではなく)基本であって実用を加えていく
濡れ衣(ぬれぎぬ):
(無実の罪を受ける,のではなく)罪を避けるために自ら被るもの
類を以て集まる×類を以て集める○
(似ているものは集まるのではなく)似ているものは同じ卦に集める
温故知新(おんこちしん):
(故きをたずねる,のではなく)死んだ何かを温めると発見がある
大同小異(だいどうしょうい):
(だいたいおなじ,ではなく)方法は一つでも結果は見方によって異なる
年年歳歳,歳々年々(ねんねんさいさい,さいさいねんねん):
1年の命の花は代りながら変らず,人は歳を重ね代らずに変る。
付和雷同×不和雷同○(ふわらいどう):
和せず人前で大声をだす
烏合の衆(うごうのしゅう):
(カラスのように統制も規律もない群衆,ではなく)項羽に合した戦闘集団
漱石枕流(そうせきちんりゅう):
礼による身分制度そのものを否定する完全な自由
嚢中の錐(のうちゅうのきり):
(才能は隠れていても現れる,ではなく)狭い場所では能力を発揮できない
満を持す(まんをじす):
(弓をひきしぼる,のではなく)徳が満ちるまでの時間を待つ
荒唐無稽(こうとうむけい):
(荒唐+無稽ではなく)荒れた唐には祭礼の酒器もない
遠慮なければ近憂あり(えんりょなければきんゆうあり):
時間ではなく距離の問題
驚天動地の新発見を楽しみにしている。
ここまで毎日書き続けられたのは,多くの人の支えがあったからだと思う。
心より感謝する。
2009年02月23日
(す)隋珠和璧(ずいしゅかへき)
隋珠和璧:
この世の最高の宝。最も価値のあるもののたとえ。
隋珠=春秋時代,隋侯(ずいこう)が命を助けた礼として大蛇から贈られたとする天下の名玉。
和璧=楚(そ)の卞和(べんか)が山中で見つけた,宝玉の原石(和氏(かし)の璧(たま))
出典:淮南子
魏(ぎ)文帝(ぶんてい)が「価値は万金を越え,貴重さは都城ほどある。」と憧れた宝玉は4つあったことを双璧で述べた。晉の垂棘,魯の璵璠,宋の結綠,楚の和璞(和氏の璧)である。さらにこの隋珠も和氏の璧に並ぶ宝玉のようである。
墨子(紀元前450年~390年頃)も「和氏之璧,隋侯之珠,三棘六異が諸侯にとっての最高の宝である。」( 墨子耕柱)と言っている。
三棘六異は九鼎 (きゅうてい)のことである。九鼎は夏(か)王禹(う)が九州(中国全土)から集めさせた青銅で鋳造した祭器である。王権の象徴として殷(いん)・周(しゅう)に引き継がれ,楚(そ)の荘王が「鼎(かなえ)の軽重(けいちょう)」を問い,秦(しん)統一の動乱で泗水に沈んだと言われている。これも相当な代物である。
さて,故事成語いろは集も京を残すのみとなった。
2000年以上も前の警句が現代に十分響くことに驚いている。
ただ,無制限に諸子百家の思想を混在させたことで焦点があいまいになった。
道・徳・仁・義・礼など語句の一人歩き,前置きのない乱用も多かった。
それを整理する意味も込めて,隋珠和璧に関係した記述を引く。
法家の韓非子が道家の老子の思想にふれた文である。韓非子解老
『人が道(どう:自然の摂理)を学んで,蓄積された知恵が徳(とく)である。
徳が充実すると外に対して光を放つようになる,この光が仁(じん)である。
仁が当たったものは反射をする,この反射した光が義(ぎ)である。
反射の仕方はものによって異なり,反射の仕方が礼(れい)である。
礼によってそのものの形や色がわかり,それを飾る言葉が文(ぶん)である。
だから,徳がないと仁が発揮できず,仁が発揮されないと義が起こらず,
義が起こらなければ礼は意味をなさず,礼に意味がなければ文は嘘になる。
..形を頼んで真情を褒めるなら実はその真情が醜いからであり,
文飾を抜きにして実質を話せないならその実質が貧弱なのである。
和氏の璧は五色の絹で飾る必要がなく,隋侯の珠は金銀で装う必要がない。
実質が美しくて,何物を以てしてもその装飾とするに足りないからである。』
(参考:明治書院新釈漢文大系韓非子上)
さらに混乱は増したかも知れない。
ただ,道・徳・仁・義・礼の論理はこの説明がもっともすっきりしている。
同義反復に陥ることがなく,なにより物理的である。
この世の最高の宝。最も価値のあるもののたとえ。
隋珠=春秋時代,隋侯(ずいこう)が命を助けた礼として大蛇から贈られたとする天下の名玉。
和璧=楚(そ)の卞和(べんか)が山中で見つけた,宝玉の原石(和氏(かし)の璧(たま))
出典:淮南子
魏(ぎ)文帝(ぶんてい)が「価値は万金を越え,貴重さは都城ほどある。」と憧れた宝玉は4つあったことを双璧で述べた。晉の垂棘,魯の璵璠,宋の結綠,楚の和璞(和氏の璧)である。さらにこの隋珠も和氏の璧に並ぶ宝玉のようである。
墨子(紀元前450年~390年頃)も「和氏之璧,隋侯之珠,三棘六異が諸侯にとっての最高の宝である。」( 墨子耕柱)と言っている。
三棘六異は九鼎 (きゅうてい)のことである。九鼎は夏(か)王禹(う)が九州(中国全土)から集めさせた青銅で鋳造した祭器である。王権の象徴として殷(いん)・周(しゅう)に引き継がれ,楚(そ)の荘王が「鼎(かなえ)の軽重(けいちょう)」を問い,秦(しん)統一の動乱で泗水に沈んだと言われている。これも相当な代物である。
さて,故事成語いろは集も京を残すのみとなった。
2000年以上も前の警句が現代に十分響くことに驚いている。
ただ,無制限に諸子百家の思想を混在させたことで焦点があいまいになった。
道・徳・仁・義・礼など語句の一人歩き,前置きのない乱用も多かった。
それを整理する意味も込めて,隋珠和璧に関係した記述を引く。
法家の韓非子が道家の老子の思想にふれた文である。韓非子解老
『人が道(どう:自然の摂理)を学んで,蓄積された知恵が徳(とく)である。
徳が充実すると外に対して光を放つようになる,この光が仁(じん)である。
仁が当たったものは反射をする,この反射した光が義(ぎ)である。
反射の仕方はものによって異なり,反射の仕方が礼(れい)である。
礼によってそのものの形や色がわかり,それを飾る言葉が文(ぶん)である。
だから,徳がないと仁が発揮できず,仁が発揮されないと義が起こらず,
義が起こらなければ礼は意味をなさず,礼に意味がなければ文は嘘になる。
..形を頼んで真情を褒めるなら実はその真情が醜いからであり,
文飾を抜きにして実質を話せないならその実質が貧弱なのである。
和氏の璧は五色の絹で飾る必要がなく,隋侯の珠は金銀で装う必要がない。
実質が美しくて,何物を以てしてもその装飾とするに足りないからである。』
(参考:明治書院新釈漢文大系韓非子上)
さらに混乱は増したかも知れない。
ただ,道・徳・仁・義・礼の論理はこの説明がもっともすっきりしている。
同義反復に陥ることがなく,なにより物理的である。
2009年02月22日
(せ)井蛙(せいあ),千丈の堤も螻蟻(ろうぎ)の穴を以て潰ゆ
「井の中の蛙と笑われようとも書き続ける。いつの日か蟻の穴から堤も崩れるだろうことを信じて。」
井蛙(せいあ):
知識や見聞の狭いことのたとえ。また,自分だけの狭い知識や見解にとらわれて,他に広い世界があることを知らないで,得意になって振舞うたとえ。小さな井戸の中にすむ蛙は,大きな海のあることを知らないという意から。世間知らず,独りよがりをいましめるときに用いられることが多い。
『井蛙(せいあ)は以て海を語るべからざるは,虚に拘(かかわ)ればなり。
(井戸の蛙に海の話をしてもわからないのは,蛙が井戸という狭い居場所にとらわれているからだ。)』荘子
(新明解故事ことわざ辞典)
千丈の堤も螻蟻(ろうぎ)の穴を以て潰ゆ:
小さな欠陥やちょっとした油断がもとで大きな失敗や損害を引き起こすということのたとえ。堅固に築いた堤も,蟻が作った小さな穴から崩れることから。
『千丈(せんじょう)の堤も,螻螘(ろうぎ)の穴を以て漏れ,百尋(ひゃくじん)の屋(おく)も,突隙(とつげき)の熛(へう)を以て焚(や)く。
(千丈の高さの堤も,おけらや蟻の作った穴から壊れ,百尋の高さの家も煙突の隙間から出る火の粉で焼けてしまう)』淮南子人閒訓
(新明解故事ことわざ辞典,ただし出典は淮南子とした)
「井蛙」の続きを読んでみよう。荘子秋水の前段を要約する。
『..夏の虫に氷の事を話してもわからないのは,自分が生きている季節だけが時だと思っているからである。
地方の人に国家の政道を話してもわからないのは,卑俗な因習に束縛されているからである。..
さて,この世の中で水の最も大なるものは海である。海にはすべての川という川が流れ込んで永久に止まることがないが,それで溢れることはない。しかし,その大きさを優れたものだと考えないのは自分が小さいからなのである。..
物の量というものは限定できないものであり,時間は流れて止まることがない。物の分限は常に変化して,事の終始は循環するものでどれが元だということがない。..
細小なものからは巨大なものを見尽くすことができず,巨大なものからは細小なものを見分けることは難しい。そもそも精とは細小なものの更に微細なものをいい,粗とは巨大なもののさらに盛大なものをいう。..』
(参考:明治書院新釈漢文大系荘子下)
見ること,知ることの限界を述べており,絶望感さえ漂う。
しかし,あることを知っているがその全体を知らないというのが,学びの原点である。
「千丈の堤も螻蟻(ろうぎ)の穴を以て潰ゆ」の続きも読んでみよう。
『..人は大きな山に躓(つまず)くことはないが,小さな蟻塚には躓く。小害を軽視し微事をおろそかにして後悔することが多く,心配事が起きてからあれこれと悩む。あたかも病人が危篤になってから良医を探すようなものである。..
そもそも人が禍(わざわい)にかかるのは,その人自らがこれを生み出しているのであり,人が福を得るのは,その人自らがこれを成し遂げているのである。..
それゆえ,知恵をはたらかせることこそが禍福の門戸であり,動静を見極めることこそが利害の枢機なのである。これをわきまえれば,百事の変化,国家の治乱も居ながらにしてつかむことができる。..』
(参考:明治書院新釈漢文大系淮南子下)
このあと塞翁が馬の逸話に続く。
知恵を働かせて,動静を見極めることが禍を福に転ずる方法のようである。
故事成語シリーズも今日を含めてあと3回で完成である。
限られた知識と知恵で政治の禍を論評する愚を重ねてきた。
黙って放置すれば更に大きな障壁になることを心配している。
立ちはだかる巨大な壁に蟻の一穴を空けられたか,気がかりである。
井蛙(せいあ):
知識や見聞の狭いことのたとえ。また,自分だけの狭い知識や見解にとらわれて,他に広い世界があることを知らないで,得意になって振舞うたとえ。小さな井戸の中にすむ蛙は,大きな海のあることを知らないという意から。世間知らず,独りよがりをいましめるときに用いられることが多い。
『井蛙(せいあ)は以て海を語るべからざるは,虚に拘(かかわ)ればなり。
(井戸の蛙に海の話をしてもわからないのは,蛙が井戸という狭い居場所にとらわれているからだ。)』荘子
(新明解故事ことわざ辞典)
千丈の堤も螻蟻(ろうぎ)の穴を以て潰ゆ:
小さな欠陥やちょっとした油断がもとで大きな失敗や損害を引き起こすということのたとえ。堅固に築いた堤も,蟻が作った小さな穴から崩れることから。
『千丈(せんじょう)の堤も,螻螘(ろうぎ)の穴を以て漏れ,百尋(ひゃくじん)の屋(おく)も,突隙(とつげき)の熛(へう)を以て焚(や)く。
(千丈の高さの堤も,おけらや蟻の作った穴から壊れ,百尋の高さの家も煙突の隙間から出る火の粉で焼けてしまう)』淮南子人閒訓
(新明解故事ことわざ辞典,ただし出典は淮南子とした)
「井蛙」の続きを読んでみよう。荘子秋水の前段を要約する。
『..夏の虫に氷の事を話してもわからないのは,自分が生きている季節だけが時だと思っているからである。
地方の人に国家の政道を話してもわからないのは,卑俗な因習に束縛されているからである。..
さて,この世の中で水の最も大なるものは海である。海にはすべての川という川が流れ込んで永久に止まることがないが,それで溢れることはない。しかし,その大きさを優れたものだと考えないのは自分が小さいからなのである。..
物の量というものは限定できないものであり,時間は流れて止まることがない。物の分限は常に変化して,事の終始は循環するものでどれが元だということがない。..
細小なものからは巨大なものを見尽くすことができず,巨大なものからは細小なものを見分けることは難しい。そもそも精とは細小なものの更に微細なものをいい,粗とは巨大なもののさらに盛大なものをいう。..』
(参考:明治書院新釈漢文大系荘子下)
見ること,知ることの限界を述べており,絶望感さえ漂う。
しかし,あることを知っているがその全体を知らないというのが,学びの原点である。
「千丈の堤も螻蟻(ろうぎ)の穴を以て潰ゆ」の続きも読んでみよう。
『..人は大きな山に躓(つまず)くことはないが,小さな蟻塚には躓く。小害を軽視し微事をおろそかにして後悔することが多く,心配事が起きてからあれこれと悩む。あたかも病人が危篤になってから良医を探すようなものである。..
そもそも人が禍(わざわい)にかかるのは,その人自らがこれを生み出しているのであり,人が福を得るのは,その人自らがこれを成し遂げているのである。..
それゆえ,知恵をはたらかせることこそが禍福の門戸であり,動静を見極めることこそが利害の枢機なのである。これをわきまえれば,百事の変化,国家の治乱も居ながらにしてつかむことができる。..』
(参考:明治書院新釈漢文大系淮南子下)
このあと塞翁が馬の逸話に続く。
知恵を働かせて,動静を見極めることが禍を福に転ずる方法のようである。
故事成語シリーズも今日を含めてあと3回で完成である。
限られた知識と知恵で政治の禍を論評する愚を重ねてきた。
黙って放置すれば更に大きな障壁になることを心配している。
立ちはだかる巨大な壁に蟻の一穴を空けられたか,気がかりである。
2009年02月21日
(も)木鷄(もっけい)
「木鷄のごとく泰然自若を装っているが,内心は失言しないかドキドキなんだろうな。」
木鷄(もっけい)
①木製の闘鶏。②真に強い者は敵に対して少しも動じないことのたとえ。出典:荘子達生(Yahoo!辞書 大辞林)
『紀渻子(きせいし)は,王のために闘鶏を訓練することになった。
十日後に王が問う。
「使えるようになったか?」
「まだでございます。今はから元気で威張っているところです。」
十日後また問う。
「いや,まだでございます。すぐとびかかろうとします。」
十日後また問う。
「いや,まだでございます。まだ睨みつけて怒っております。」
十日後また問う。
「もうそろそろよいでしょう。周囲が騒いでも全く動じません。
まるで木彫りの鶏のようで,徳が全身に充実しております。
他の鶏はとびかかることもできず,一目見るなり逃げて行きます。」..』
王が持っていた闘鶏だからもともと力は強かったのだろう。
紀渻子は鶏に戦う技術ではなく精神面の充実を教えたということである。
荘子は,人についても同様に書いている。
『顏淵(がんえん)は孔子(こうし)に尋ねる。
「舟を漕(こ)ぐ術は学べるのかについて,
泳(およ)ぎの上手な者であれば何回か繰り返せば漕げるようになり,
潜(もぐ)りの達人であればすぐに漕げるようになる,
と聞きましたがどういうことでしょうか?」
孔子が答えた。
「泳ぎの上手な者は,水のかき方が巧みですぐに慣れるからだ。
潜りの達人は,水に恐れがないから深い淵でも陸上と変わらない動きができるからだ。
たとえば,物を賭けて弓を競うときには,賭ける物ががらくたなら上手に当たるだろう。
しかし,黄金を賭けるとなると心が乱れてなかなか当たらない。
技量は同じでも外物に心が傾くのである。」...』
剣豪の宮本武蔵は,不動心を問われて敷居の上を歩いて見せた。
もし,下が畳ではなく千尋の谷であれば同様に歩けるか?
外物に心が傾くことのない達人の境地である。
木鷄は,いかなることにも心を乱されず,不断の努力で体得した境地である。
無気力,無責任,無感動..その果ての厚顔無恥とは似て非なるものである。
困窮に喘ぐ国民が注視する国会で,舟を漕ぐような選挙の達人は不用である。
木鷄(もっけい)
①木製の闘鶏。②真に強い者は敵に対して少しも動じないことのたとえ。出典:荘子達生(Yahoo!辞書 大辞林)
『紀渻子(きせいし)は,王のために闘鶏を訓練することになった。
十日後に王が問う。
「使えるようになったか?」
「まだでございます。今はから元気で威張っているところです。」
十日後また問う。
「いや,まだでございます。すぐとびかかろうとします。」
十日後また問う。
「いや,まだでございます。まだ睨みつけて怒っております。」
十日後また問う。
「もうそろそろよいでしょう。周囲が騒いでも全く動じません。
まるで木彫りの鶏のようで,徳が全身に充実しております。
他の鶏はとびかかることもできず,一目見るなり逃げて行きます。」..』
王が持っていた闘鶏だからもともと力は強かったのだろう。
紀渻子は鶏に戦う技術ではなく精神面の充実を教えたということである。
荘子は,人についても同様に書いている。
『顏淵(がんえん)は孔子(こうし)に尋ねる。
「舟を漕(こ)ぐ術は学べるのかについて,
泳(およ)ぎの上手な者であれば何回か繰り返せば漕げるようになり,
潜(もぐ)りの達人であればすぐに漕げるようになる,
と聞きましたがどういうことでしょうか?」
孔子が答えた。
「泳ぎの上手な者は,水のかき方が巧みですぐに慣れるからだ。
潜りの達人は,水に恐れがないから深い淵でも陸上と変わらない動きができるからだ。
たとえば,物を賭けて弓を競うときには,賭ける物ががらくたなら上手に当たるだろう。
しかし,黄金を賭けるとなると心が乱れてなかなか当たらない。
技量は同じでも外物に心が傾くのである。」...』
剣豪の宮本武蔵は,不動心を問われて敷居の上を歩いて見せた。
もし,下が畳ではなく千尋の谷であれば同様に歩けるか?
外物に心が傾くことのない達人の境地である。
木鷄は,いかなることにも心を乱されず,不断の努力で体得した境地である。
無気力,無責任,無感動..その果ての厚顔無恥とは似て非なるものである。
困窮に喘ぐ国民が注視する国会で,舟を漕ぐような選挙の達人は不用である。