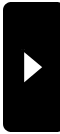2009年01月31日
(う)烏合の衆
「政治理念はおかまいなしに,与党か野党かで決めるなんてまさに烏合(うごう)の衆・議員だ。」
烏合の衆(うごうのしゅう):ただ寄り集まって騒ぐだけで,統制も規律もない群衆,または軍勢のたとえ。鳥の中でも烏(からす)の群れは,寄り集まって騒ぐだけで,統制も規律もないところから。
出典:後漢書(新明解故事ことわざ辞典)
カラスは人の顔を覚えたり,自販機を使えたり,と賢い鳥である。
さらには「烏に反哺(はんぽ)の孝あり」とかなかなか親孝行である。
出来の悪い人間共と一緒にされたらカラスの沽券(こけん)にかかわる問題だ。
「烏合」で検索してみると,東觀漢記で1回,後漢書4回で使われている。
後漢書の1回は東觀漢記の引用と思われる同一の文があった。
つごう4文が「烏合」が初期に使われたと思われる文である。
不思議なことにすべてが「烏合之眾」の形で使われている。
4文を解釈してみる。
①烏合之眾をはしらせて,馬にまたがり敵に突き進み,向う所をたちまち平げた。
②漢が起こり,悪賢い烏合之眾を追い払って,天下の隅々から追い払った。
③騎兵をもちいて烏合之眾をふみにじり,くさった木を折るようにたやすく降伏させた。
④王郎は,烏合之眾を集めてはしらせ,遂に燕と趙の地を脅かした。
どうも「烏合之眾」は戦争に関係する集団のようである。
そして,「烏合」(カラスのあつまり)の眾ではなく,いきなり「烏合之眾」の一語で使われている。
「烏合之眾」は,単なる人の寄せ集めではなく,
戦争を行う訓練された統制のとれた集団だったのではないだろうか?
たとえば,日本の戦国時代の鉄砲で武装した根来衆や
秀吉に仕えた御伽衆のような職能集団ではなかったか。
ではどこの国の軍隊だったのか?
漢が成立する当時に,敵対する集団であったのだから項羽の軍団と考えるのが素直である。
つまり,本当は「(項)羽に合わさった集団」と言いたかったのだ。
だが,実名を使うのをはばかって発音の似た「烏」としたのではないか。
あるいは,さらにそこに蔑みの意味も込めているのではないだろうか。
その後,王郎の反乱の際に,敵対する軍隊の意味として「烏合之眾」を使った。
それから次第にカラスの印象だけが強まって現在の意味になった。
...これでカラスの濡れ衣も晴れるであろう。
生ゴミを漁っているカラスよりも,選挙準備に汲々とする政治家のほうがさもしく見える。
一所懸命さが見えないのだ。
----------------------------------------------------------------------------------------------
【今東帝無尺寸之柄,驅烏合之眾,跨馬陷敵,所向輒平。】東觀漢記載記公孫述
【漢起,驅輕黠烏合之眾,不當天下萬分之一,而旌旃之所撝及,書文之所通被,莫不折戈頓顙,爭受職命。】後漢書劉玄劉盆子列傳
【今東帝無尺土之柄,驅烏合之眾,跨馬陷敵,所向輒平。】後漢書隗囂公孫述列傳
【我至長安,與國家陳漁陽、上谷兵馬之用,還出太原、代郡,反覆數十日,歸發突騎以轔烏合之眾,如摧枯折腐耳。】後漢書耿弇列傳
【又卜者王郎,假名因埶,驅集烏合之眾,遂震燕、趙之地。】後漢書任李萬邳劉耿列傳
烏合の衆(うごうのしゅう):ただ寄り集まって騒ぐだけで,統制も規律もない群衆,または軍勢のたとえ。鳥の中でも烏(からす)の群れは,寄り集まって騒ぐだけで,統制も規律もないところから。
出典:後漢書(新明解故事ことわざ辞典)
カラスは人の顔を覚えたり,自販機を使えたり,と賢い鳥である。
さらには「烏に反哺(はんぽ)の孝あり」とかなかなか親孝行である。
出来の悪い人間共と一緒にされたらカラスの沽券(こけん)にかかわる問題だ。
「烏合」で検索してみると,東觀漢記で1回,後漢書4回で使われている。
後漢書の1回は東觀漢記の引用と思われる同一の文があった。
つごう4文が「烏合」が初期に使われたと思われる文である。
不思議なことにすべてが「烏合之眾」の形で使われている。
4文を解釈してみる。
①烏合之眾をはしらせて,馬にまたがり敵に突き進み,向う所をたちまち平げた。
②漢が起こり,悪賢い烏合之眾を追い払って,天下の隅々から追い払った。
③騎兵をもちいて烏合之眾をふみにじり,くさった木を折るようにたやすく降伏させた。
④王郎は,烏合之眾を集めてはしらせ,遂に燕と趙の地を脅かした。
どうも「烏合之眾」は戦争に関係する集団のようである。
そして,「烏合」(カラスのあつまり)の眾ではなく,いきなり「烏合之眾」の一語で使われている。
「烏合之眾」は,単なる人の寄せ集めではなく,
戦争を行う訓練された統制のとれた集団だったのではないだろうか?
たとえば,日本の戦国時代の鉄砲で武装した根来衆や
秀吉に仕えた御伽衆のような職能集団ではなかったか。
ではどこの国の軍隊だったのか?
漢が成立する当時に,敵対する集団であったのだから項羽の軍団と考えるのが素直である。
つまり,本当は「(項)羽に合わさった集団」と言いたかったのだ。
だが,実名を使うのをはばかって発音の似た「烏」としたのではないか。
あるいは,さらにそこに蔑みの意味も込めているのではないだろうか。
その後,王郎の反乱の際に,敵対する軍隊の意味として「烏合之眾」を使った。
それから次第にカラスの印象だけが強まって現在の意味になった。
...これでカラスの濡れ衣も晴れるであろう。
生ゴミを漁っているカラスよりも,選挙準備に汲々とする政治家のほうがさもしく見える。
一所懸命さが見えないのだ。
----------------------------------------------------------------------------------------------
【今東帝無尺寸之柄,驅烏合之眾,跨馬陷敵,所向輒平。】東觀漢記載記公孫述
【漢起,驅輕黠烏合之眾,不當天下萬分之一,而旌旃之所撝及,書文之所通被,莫不折戈頓顙,爭受職命。】後漢書劉玄劉盆子列傳
【今東帝無尺土之柄,驅烏合之眾,跨馬陷敵,所向輒平。】後漢書隗囂公孫述列傳
【我至長安,與國家陳漁陽、上谷兵馬之用,還出太原、代郡,反覆數十日,歸發突騎以轔烏合之眾,如摧枯折腐耳。】後漢書耿弇列傳
【又卜者王郎,假名因埶,驅集烏合之眾,遂震燕、趙之地。】後漢書任李萬邳劉耿列傳
2009年01月30日
(む)矛盾
「だけど『平和のための戦争』って矛盾してないか?報復の繰り返しで死体は増える一方だ。」
矛盾(むじゅん):前に言ったことと後に言ったことのつじつまが合わないこと。
論理が一貫しないこと。矛=やり・ほこ。盾=たて。
『楚の国の人が矛(ほこ)と盾(たて)を売っていた。
その商人は盾を自慢して「この盾はとても堅く,どんなものでも突き通すことはできない。」と言った。
次に矛を自慢して「この矛はとても鋭く,どんなものでも突き通すことができる。」と言った。そこである人が
「では,その矛でその盾を突いたらどうなるのか?」と聞くと,商人は答えることができなかった。』韓非子
(新明解故事ことわざ辞典)
高く買ってもらうための誇張を逆手に取られた格好だ。
けれど,商人は黙ってしまうのではなく,こう答えるべきではなかったか。
「そうなんですよお客さん,私も大変興味があります。ぜひ両方とも買って試してみてください。」
矛か盾の片方だけを置いていたら,あるいは時間をずらして売っていたら,この矛盾は発見も証明できない。
一人の人間が同時に両方を揃えてしまったことが,問題を発生させたのである。
さて,現代日本の経済政策(金融)の矛盾を一つ上げよう。
発端は,BIS規制である。これによって次の命題が与えられた。
「銀行は,①債権を時価評価し,②不良債権を早急に処理し,③十分に貸倒引当金を積み,その上で自己資本比率8%を維持すること。」
①は債権の価値が減少すると資産が減り,自己資本が減る。
②は不良債権を処理すると利益が減少し,自己資本が減る。
③は負債が増加し(又は資産が減少し),自己資本が減る。
「自己資本が減ることをしながら,自己資本を維持する。」これが第1の矛盾である。
自己資本比率が8%より低いと国際業務ができない。
それで,公的資金を7.5兆円を投入し,自己資本を強化する。
「経営の知恵や努力でなく,国民の金で体裁を繕った。」これが第2の矛盾である。
...これは今回の緊急経済対策ではない。1999年に行われたことである。
それによって,
①~③の危険が高いところ(倒産しそうな会社,自己資本の小さい会社..)には貸出さなくなる。
これが「貸し渋り」「貸しはがし」の実態である。
資金のない会社は事業の拡大ができなくなる。資金繰りに困った会社は倒産する。
銀行の使命は,預金者から資金を調達し企業に貸し出すこと(間接金融)だが,
「本来の使命を放棄し,預かった資金を金融証券に投資した」これが第3の矛盾である。
以上が「失われた10年」の金融視点の側面と矛盾の連鎖である。
10年後成立した今回の二次補正予算の中身は
④資金繰り対策(信用保証協会の緊急保証枠他) 30兆円
⑤銀行等保有株式取得機構の政府保証枠 20兆円
⑥改正金融機能強化法に基づく国の資本参加枠 12兆円
であった。わかりやすく言うと
④中小企業への貸出は焦げ付いたら国が保証するから,不良債権になることがない。
⑤銀行が持っている値段の下がった株式は国が買い取るから,資産は目減りしない。
⑥それでもだめなら資本を注入する。または国有化する。
ということなのだ。10年経って7.5兆円が62兆円に増えてしまった。
小さな矛盾の積み重ねが大きな不条理を生んでいるのだ。
2兆円ごときで騒いでいる場合ではない。
政-官-業,利権連鎖の盾はいよいよ強靭になっている。
ブログごときのひ弱な矛では針の先ほどの傷もつくまい。
------------------------------------------------------------------------------------------
【人有鬻矛與楯者,譽其楯之堅,物莫能陷也,俄而又譽其矛曰:‘吾矛之利,物無不陷也。’人應之曰:‘以子之矛陷子之楯何如?’其人弗能應也。”】韓非子難勢
矛盾(むじゅん):前に言ったことと後に言ったことのつじつまが合わないこと。
論理が一貫しないこと。矛=やり・ほこ。盾=たて。
『楚の国の人が矛(ほこ)と盾(たて)を売っていた。
その商人は盾を自慢して「この盾はとても堅く,どんなものでも突き通すことはできない。」と言った。
次に矛を自慢して「この矛はとても鋭く,どんなものでも突き通すことができる。」と言った。そこである人が
「では,その矛でその盾を突いたらどうなるのか?」と聞くと,商人は答えることができなかった。』韓非子
(新明解故事ことわざ辞典)
高く買ってもらうための誇張を逆手に取られた格好だ。
けれど,商人は黙ってしまうのではなく,こう答えるべきではなかったか。
「そうなんですよお客さん,私も大変興味があります。ぜひ両方とも買って試してみてください。」
矛か盾の片方だけを置いていたら,あるいは時間をずらして売っていたら,この矛盾は発見も証明できない。
一人の人間が同時に両方を揃えてしまったことが,問題を発生させたのである。
さて,現代日本の経済政策(金融)の矛盾を一つ上げよう。
発端は,BIS規制である。これによって次の命題が与えられた。
「銀行は,①債権を時価評価し,②不良債権を早急に処理し,③十分に貸倒引当金を積み,その上で自己資本比率8%を維持すること。」
①は債権の価値が減少すると資産が減り,自己資本が減る。
②は不良債権を処理すると利益が減少し,自己資本が減る。
③は負債が増加し(又は資産が減少し),自己資本が減る。
「自己資本が減ることをしながら,自己資本を維持する。」これが第1の矛盾である。
自己資本比率が8%より低いと国際業務ができない。
それで,公的資金を7.5兆円を投入し,自己資本を強化する。
「経営の知恵や努力でなく,国民の金で体裁を繕った。」これが第2の矛盾である。
...これは今回の緊急経済対策ではない。1999年に行われたことである。
それによって,
①~③の危険が高いところ(倒産しそうな会社,自己資本の小さい会社..)には貸出さなくなる。
これが「貸し渋り」「貸しはがし」の実態である。
資金のない会社は事業の拡大ができなくなる。資金繰りに困った会社は倒産する。
銀行の使命は,預金者から資金を調達し企業に貸し出すこと(間接金融)だが,
「本来の使命を放棄し,預かった資金を金融証券に投資した」これが第3の矛盾である。
以上が「失われた10年」の金融視点の側面と矛盾の連鎖である。
10年後成立した今回の二次補正予算の中身は
④資金繰り対策(信用保証協会の緊急保証枠他) 30兆円
⑤銀行等保有株式取得機構の政府保証枠 20兆円
⑥改正金融機能強化法に基づく国の資本参加枠 12兆円
であった。わかりやすく言うと
④中小企業への貸出は焦げ付いたら国が保証するから,不良債権になることがない。
⑤銀行が持っている値段の下がった株式は国が買い取るから,資産は目減りしない。
⑥それでもだめなら資本を注入する。または国有化する。
ということなのだ。10年経って7.5兆円が62兆円に増えてしまった。
小さな矛盾の積み重ねが大きな不条理を生んでいるのだ。
2兆円ごときで騒いでいる場合ではない。
政-官-業,利権連鎖の盾はいよいよ強靭になっている。
ブログごときのひ弱な矛では針の先ほどの傷もつくまい。
------------------------------------------------------------------------------------------
【人有鬻矛與楯者,譽其楯之堅,物莫能陷也,俄而又譽其矛曰:‘吾矛之利,物無不陷也。’人應之曰:‘以子之矛陷子之楯何如?’其人弗能應也。”】韓非子難勢
2009年01月29日
(ら)雷同
「賢者は,協調はするが雷同はしない。愚者は、雷同はするが協調はしない。」
付和雷同(ふわらいどう):自分にしっかりとした考えがなく,軽々しく他人の意見に同調すること。単に「雷同」ともいう。付和=わけもなく他人のことばに賛成すること。雷同=雷が鳴ると万物がそれに応じて響く意から,むやみに他人の言動に同調すること。出典禮記
(新明解故事ことわざ辞典)
雷が鳴ると万物が響くのだろうか。驚いてすくんでしまう気もする。原文を調べてみた。
『將が席に即(つ)くときは,容(かたち)を怍(は)じないように。両手で衣の尺を齊(そろ)えてからげ,衣を撥(は)ねず,足は蹶(つま)づかず。先生が書や琴に向かわれているときは,遷(うご)くことなく坐り,ものをとび越えてはいけない。..長者は言葉を儳(おざなりに)しない。容(かたち)を正しくし,恭しく聴きなさい。..』
どうも礼儀作法の話のようである。そのあとに【毋剿說,毋雷同。】と続く。
【毋剿說】は「演説を剿(さえぎ)らず」が続きそうだ。そして【毋雷同】は「同(あつまり)では雷(大声)をださない。」くらいが適当ではないだろうか。
礼儀作法の話が,ここにきていきなり「他人の意見に同調..云々」などでは,大仰すぎるし,主体があいまいになる。「雷同」の本来の意味は「人の多い所で大声を出す」ことだったのではないだろうか。
熟語として「雷同」と一緒に使われる言葉に「付和雷同」がある。「附和雷同」と書かれる場合もある。ただし「不和雷同」は間違いとされている。
実はこの「フワ」の語源ははっきりしていない。「雷同」の意味があまりに限定されたため,うまく説明できないのかも知れない。
ところが,「同」が集まりで「雷」が大声だとすると,今は劣勢の「不和雷同」が俄然,真実味を帯びる。ずばり「和せず怒鳴り合っている集合」なのである。
「雷同」は,二股膏薬のごとく定見節操のない政治家と野次と罵声だけが得意な政治家をひとくくりにする。愚者の政治はまだまだ続く。
----------------------------------------------------------------------------------------------------
【將即席,容毋怍。兩手摳衣去齊尺。衣毋撥,足毋蹶。先生書策琴瑟在前,坐而遷之,戒勿越。虛坐盡後,食坐盡前。坐必安,執爾顏。長者不及,毋儳言。正爾容,聽必恭。毋剿說,毋雷同。必則古昔,稱先王。】禮記曲禮上
付和雷同(ふわらいどう):自分にしっかりとした考えがなく,軽々しく他人の意見に同調すること。単に「雷同」ともいう。付和=わけもなく他人のことばに賛成すること。雷同=雷が鳴ると万物がそれに応じて響く意から,むやみに他人の言動に同調すること。出典禮記
(新明解故事ことわざ辞典)
雷が鳴ると万物が響くのだろうか。驚いてすくんでしまう気もする。原文を調べてみた。
『將が席に即(つ)くときは,容(かたち)を怍(は)じないように。両手で衣の尺を齊(そろ)えてからげ,衣を撥(は)ねず,足は蹶(つま)づかず。先生が書や琴に向かわれているときは,遷(うご)くことなく坐り,ものをとび越えてはいけない。..長者は言葉を儳(おざなりに)しない。容(かたち)を正しくし,恭しく聴きなさい。..』
どうも礼儀作法の話のようである。そのあとに【毋剿說,毋雷同。】と続く。
【毋剿說】は「演説を剿(さえぎ)らず」が続きそうだ。そして【毋雷同】は「同(あつまり)では雷(大声)をださない。」くらいが適当ではないだろうか。
礼儀作法の話が,ここにきていきなり「他人の意見に同調..云々」などでは,大仰すぎるし,主体があいまいになる。「雷同」の本来の意味は「人の多い所で大声を出す」ことだったのではないだろうか。
熟語として「雷同」と一緒に使われる言葉に「付和雷同」がある。「附和雷同」と書かれる場合もある。ただし「不和雷同」は間違いとされている。
実はこの「フワ」の語源ははっきりしていない。「雷同」の意味があまりに限定されたため,うまく説明できないのかも知れない。
ところが,「同」が集まりで「雷」が大声だとすると,今は劣勢の「不和雷同」が俄然,真実味を帯びる。ずばり「和せず怒鳴り合っている集合」なのである。
「雷同」は,二股膏薬のごとく定見節操のない政治家と野次と罵声だけが得意な政治家をひとくくりにする。愚者の政治はまだまだ続く。
----------------------------------------------------------------------------------------------------
【將即席,容毋怍。兩手摳衣去齊尺。衣毋撥,足毋蹶。先生書策琴瑟在前,坐而遷之,戒勿越。虛坐盡後,食坐盡前。坐必安,執爾顏。長者不及,毋儳言。正爾容,聽必恭。毋剿說,毋雷同。必則古昔,稱先王。】禮記曲禮上
2009年01月28日
(な)鳴かず飛ばず
「走攻守そろった四番候補で入団したが,もう三年鳴かず飛ばずでトレード話まで持ち上がっている。」
三年飛ばず鳴かず(とばずなかず):将来,大いに活躍しようとしてじっと機会を待っているさまをいう。また,何もしないで過ごすことも言う。出典史記,類義:鳴かず飛ばず。
(新明解故事ことわざ辞典)
傍から見ていても,機会を待っているのか,無為に過ごしているのか,の見分けはつきにくい。現在は後者の意味で使われるのがほとんどであろう。
当ブログでも取り上げた斉桓公,晋文公に続く春秋の覇者,楚(そ)の荘王(そうおう)(在位前614年-591年)にまつわる故事である。この故事は当然前者の意味である。(後者であれば逸話になる前にまず命がつながらない)
荘王は即位後3年の間,政治を顧みず,酒宴に明け暮れ,『余を諫める者には死を与える』と命令していた。
伍舉が諫めようとしたときにも王は左に鄭姬,右に越女を抱いて,音楽に耽っていた。
伍舉は「謎かけ」で王に問いかけた。
「ある鳥が3年の間,全く飛ばず,全く鳴きませんでした。この鳥の名は何と言うのでしょうか?」
荘王は
「その鳥は一旦飛び立てば天まで届き,一旦鳴けば人を驚かせるだろう。お前の言わんとする事は解っている。下がれ。」
と言った。さらに数か月淫蕩は激しくなっていった。
堪りかねて蘇従が諫めた。
「(諫める者には死を与える)との命令を聞かなかったのか?」
と王が言うと
「我が身を殺して,君を明君にすることが臣(わたし)の願いです」
と蘇従は答えた。これを聞いて王は淫樂をやめ,政治に取り組み,数百人の佞臣を罰し,数百人の忠臣を登用し,伍舉と蘇從に政治を任せたので,国中の人々はよろこんだ。(史記)
荘王は3年間、愚かな振りをする事で家臣の人物を見定めていた。(とは書かれていないが)
ここからじっと機会を待つ意味の故事成語となった。
同様の話が戦国田斉の威王(在位前379年-343年)にもある。こちらはさらに長く9年の雌伏だったという。
織田信長の「おおたわけ」,大石内蔵助の「昼行灯(あんどん)」
大きな志を持つ者はどこでも最初は鳴かず飛ばずである。
だから,日本国の新しい指導者をわずか4ヶ月でなじるのは早計かも知れぬ。
それより,それを諫めるべき忠臣の少ないことを哀しむ。
彼らはよく飛び回り,よく鳴くが,命を賭して主を諫めようとはしない。
「けんけん」とかまびすしい鳥は決して高くは翔べず,狐の餌になるだけである。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
【莊王即位三年,不出號令,日夜為樂,令國中曰:“有敢諫者死無赦!”伍舉入諫。莊王左抱鄭姬,右抱越女,坐鐘鼓之閒。伍舉曰:“願有進隱。”曰:“有鳥在於阜,三年不蜚不鳴,是何鳥也?”莊王曰:“三年不蜚,蜚將沖天;三年不鳴,鳴將驚人。舉退矣,吾知之矣。”居數月,淫益甚。大夫蘇從乃入諫。王曰:“若不聞令乎?”對曰:“殺身以明君,臣之願也。”於是乃罷淫樂,聽政,所誅者數百人,所進者數百人,任伍舉、蘇從以政,國人大說。是歲滅庸。六年,伐宋,獲五百乘。】史記楚世家
三年飛ばず鳴かず(とばずなかず):将来,大いに活躍しようとしてじっと機会を待っているさまをいう。また,何もしないで過ごすことも言う。出典史記,類義:鳴かず飛ばず。
(新明解故事ことわざ辞典)
傍から見ていても,機会を待っているのか,無為に過ごしているのか,の見分けはつきにくい。現在は後者の意味で使われるのがほとんどであろう。
当ブログでも取り上げた斉桓公,晋文公に続く春秋の覇者,楚(そ)の荘王(そうおう)(在位前614年-591年)にまつわる故事である。この故事は当然前者の意味である。(後者であれば逸話になる前にまず命がつながらない)
荘王は即位後3年の間,政治を顧みず,酒宴に明け暮れ,『余を諫める者には死を与える』と命令していた。
伍舉が諫めようとしたときにも王は左に鄭姬,右に越女を抱いて,音楽に耽っていた。
伍舉は「謎かけ」で王に問いかけた。
「ある鳥が3年の間,全く飛ばず,全く鳴きませんでした。この鳥の名は何と言うのでしょうか?」
荘王は
「その鳥は一旦飛び立てば天まで届き,一旦鳴けば人を驚かせるだろう。お前の言わんとする事は解っている。下がれ。」
と言った。さらに数か月淫蕩は激しくなっていった。
堪りかねて蘇従が諫めた。
「(諫める者には死を与える)との命令を聞かなかったのか?」
と王が言うと
「我が身を殺して,君を明君にすることが臣(わたし)の願いです」
と蘇従は答えた。これを聞いて王は淫樂をやめ,政治に取り組み,数百人の佞臣を罰し,数百人の忠臣を登用し,伍舉と蘇從に政治を任せたので,国中の人々はよろこんだ。(史記)
荘王は3年間、愚かな振りをする事で家臣の人物を見定めていた。(とは書かれていないが)
ここからじっと機会を待つ意味の故事成語となった。
同様の話が戦国田斉の威王(在位前379年-343年)にもある。こちらはさらに長く9年の雌伏だったという。
織田信長の「おおたわけ」,大石内蔵助の「昼行灯(あんどん)」
大きな志を持つ者はどこでも最初は鳴かず飛ばずである。
だから,日本国の新しい指導者をわずか4ヶ月でなじるのは早計かも知れぬ。
それより,それを諫めるべき忠臣の少ないことを哀しむ。
彼らはよく飛び回り,よく鳴くが,命を賭して主を諫めようとはしない。
「けんけん」とかまびすしい鳥は決して高くは翔べず,狐の餌になるだけである。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
【莊王即位三年,不出號令,日夜為樂,令國中曰:“有敢諫者死無赦!”伍舉入諫。莊王左抱鄭姬,右抱越女,坐鐘鼓之閒。伍舉曰:“願有進隱。”曰:“有鳥在於阜,三年不蜚不鳴,是何鳥也?”莊王曰:“三年不蜚,蜚將沖天;三年不鳴,鳴將驚人。舉退矣,吾知之矣。”居數月,淫益甚。大夫蘇從乃入諫。王曰:“若不聞令乎?”對曰:“殺身以明君,臣之願也。”於是乃罷淫樂,聽政,所誅者數百人,所進者數百人,任伍舉、蘇從以政,國人大說。是歲滅庸。六年,伐宋,獲五百乘。】史記楚世家
2009年01月27日
(ね)年歳(ねんさい)
「年々歳々花相似たり,歳々年々人同じからず」
自然は変わらないのに,人の世は変わりやすいということ。人の世のはかなさをいうことば。毎年,花は同じように咲くが,それを見る人は年ごとに違っているの意から。
(新明解故事ことわざ辞典)
劉希夷(りゅうきい)「白頭を悲しむ翁に代わりて吟う」 のなかの一文である。
ここで言っている花は桃や李(すもも)の木に咲く花である。その咲いて散りゆくさまを人生に重ねて詠んでいる。
確かに「はかない」があまり切なくない。
ゴンチ流に解釈すると,
「1年で咲いて散る花はどの年も似ているのに,歳を重ねていく人間は1年前と同じではない。」
ということである。つまり,過ぎゆく時間のはかなさではなく,
「花は代わりながら変わらず,人は代わらずに変わっていく」
という逆説こそが切なさの原因なのである。
だからこそ「年々歳々・・歳々年々・・」と,「年」と「歳」の順を入れ替える必要性があったのだろう。
「年」も「歳」も,みのる,とし,など意味は同じであるが,なりたちは異なる。
年(ねん):禾(いね)の実がふくらみみのるさま。禾実が実る周期。
歳(さい):収穫時にまさかりでいけにえを裂いたさま。収穫から収穫までのめぐり。
(新字源)
一言で言うと,「年」は自然に進むが「歳」は収穫しないと進まないようである。
同じように,論語にある「日月逝きぬ,歳我とともにせず」は「(学問を行わなくても)月日は私を待たずに進む」という摂理ではなく「(学問を行わなければ)月日が過ぎても収穫がない」という論理になる。
さて,孟子も「歳」を善い意味に使っている。
「昔の明君(めいくん)が民のなりわいを定めるときは,その収入で父母を大事にし,妻子を養って,樂歲(豊年)には満腹になり、凶年(飢饉)にも死ぬことはなかった。そのあとで,民を善に驅(か)り立て,民はすすんで従ったのである。ところが今の制度では,父母に満足なことができず,妻子を安心して養うことができず,樂歲でも絶えず苦しく,凶年には死を免れることが出来ない。」
先人の知恵の収穫はまだまだ先のようである。
---------------------------------------------------------------------------------------------
【..已見松柏摧爲薪,更闻桑田變成海。..年年歲歲花相似,歲歲年年人不同。】代悲白頭吟,劉希夷全文
【日月逝矣,歲不我與】 論語陽貨
【是故明君制民之產,必使仰足以事父母,俯足以畜妻子,樂歲終身飽,凶年免於死亡。然後驅而之善,故民之從之也輕。今也制民之產,仰不足以事父母,俯不足以畜妻子,樂歲終身苦,凶年不免於死亡。】孟子梁惠王上
自然は変わらないのに,人の世は変わりやすいということ。人の世のはかなさをいうことば。毎年,花は同じように咲くが,それを見る人は年ごとに違っているの意から。
(新明解故事ことわざ辞典)
劉希夷(りゅうきい)「白頭を悲しむ翁に代わりて吟う」 のなかの一文である。
ここで言っている花は桃や李(すもも)の木に咲く花である。その咲いて散りゆくさまを人生に重ねて詠んでいる。
確かに「はかない」があまり切なくない。
ゴンチ流に解釈すると,
「1年で咲いて散る花はどの年も似ているのに,歳を重ねていく人間は1年前と同じではない。」
ということである。つまり,過ぎゆく時間のはかなさではなく,
「花は代わりながら変わらず,人は代わらずに変わっていく」
という逆説こそが切なさの原因なのである。
だからこそ「年々歳々・・歳々年々・・」と,「年」と「歳」の順を入れ替える必要性があったのだろう。
「年」も「歳」も,みのる,とし,など意味は同じであるが,なりたちは異なる。
年(ねん):禾(いね)の実がふくらみみのるさま。禾実が実る周期。
歳(さい):収穫時にまさかりでいけにえを裂いたさま。収穫から収穫までのめぐり。
(新字源)
一言で言うと,「年」は自然に進むが「歳」は収穫しないと進まないようである。
同じように,論語にある「日月逝きぬ,歳我とともにせず」は「(学問を行わなくても)月日は私を待たずに進む」という摂理ではなく「(学問を行わなければ)月日が過ぎても収穫がない」という論理になる。
さて,孟子も「歳」を善い意味に使っている。
「昔の明君(めいくん)が民のなりわいを定めるときは,その収入で父母を大事にし,妻子を養って,樂歲(豊年)には満腹になり、凶年(飢饉)にも死ぬことはなかった。そのあとで,民を善に驅(か)り立て,民はすすんで従ったのである。ところが今の制度では,父母に満足なことができず,妻子を安心して養うことができず,樂歲でも絶えず苦しく,凶年には死を免れることが出来ない。」
先人の知恵の収穫はまだまだ先のようである。
---------------------------------------------------------------------------------------------
【..已見松柏摧爲薪,更闻桑田變成海。..年年歲歲花相似,歲歲年年人不同。】代悲白頭吟,劉希夷全文
【日月逝矣,歲不我與】 論語陽貨
【是故明君制民之產,必使仰足以事父母,俯足以畜妻子,樂歲終身飽,凶年免於死亡。然後驅而之善,故民之從之也輕。今也制民之產,仰不足以事父母,俯不足以畜妻子,樂歲終身苦,凶年不免於死亡。】孟子梁惠王上