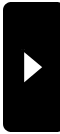2009年02月04日
(く)口に糊する
「年金で糊口をしのいでいる老身には,渡りで3億円と聞いてもピンとこないねえ。いったいそのお方はどこのどなた様でどんなお仕事をなさったんだい?」
口に糊する(くちにのりする):何とか貧しい生計を立てることのたとえ。かゆをすする意から。「口を糊する」「糊口」ともいう。やっとのことで食べ,何とか暮らしていくことを「糊口をしのぐ」という。糊する=かゆをすする。転じて,やっと暮らしを立てること。
(新明解故事ことわざ辞典)
口に糊すると聞けば,大坂町奉行所の元与力大塩平八郎の乱(1837年)を思い出す。
『天保の飢饉(1833-36年)により大阪の商業は衰退し,仕事に就くことも,食べることも簡単ではなくなって,餓死する者もあった。平八郎はそれを見かねて,救済のため私財を投げ出し,ついには蔵書までも売りつくした。それでも豪商たちは買い占めをやめず,賄賂を受け取っていた奉行所も無関心を装った。ついに平八郎は暴挙にでて,政府や民間の蔵を打ち壊して一時の救済に充てることにした。』大阪城誌(小野清,1899)とある。
この『仕事に就くことも,食べることも簡単ではない』の原文が【業ノ手ニ執ル可キ無ク、食ノ口ニ糊ス可キ無ク】である。
私財をなげうって庶民のために尽くす。(反逆者の汚名を着ることになっても)
このような義臣のいたことを誇りに思う。
渡りを禁ずる,このたびの公務員改革は明治以来の快挙という。
できればもう少し遡って天保の義臣を顕彰して欲しいものだ。
さて,その語源となった言葉は史記にある。
「伍子胥(ごししょ)は,夜歩き昼は隠れて,陵水にいたる。口に糊することなく..呉に到着し,闔閭(こうりょ)をその王とした」(史記)
伍子胥は孫武(そんぶ:孫子の兵法の著者)と共に闔閭を補佐し,楚の首都を陥落し,闔閭は斉桓公,晋文公,楚荘王に続く,春秋の覇者となった。
----------------------------------------------------------------------------------------------
【伍子胥橐載而出昭關,夜行晝伏,至於陵水,無以糊其口,厀行蒲伏,稽首肉袒,鼓腹吹篪,乞食於吳市,卒興吳國,闔閭為伯。】史記范睢蔡澤列傳
口に糊する(くちにのりする):何とか貧しい生計を立てることのたとえ。かゆをすする意から。「口を糊する」「糊口」ともいう。やっとのことで食べ,何とか暮らしていくことを「糊口をしのぐ」という。糊する=かゆをすする。転じて,やっと暮らしを立てること。
(新明解故事ことわざ辞典)
口に糊すると聞けば,大坂町奉行所の元与力大塩平八郎の乱(1837年)を思い出す。
『天保の飢饉(1833-36年)により大阪の商業は衰退し,仕事に就くことも,食べることも簡単ではなくなって,餓死する者もあった。平八郎はそれを見かねて,救済のため私財を投げ出し,ついには蔵書までも売りつくした。それでも豪商たちは買い占めをやめず,賄賂を受け取っていた奉行所も無関心を装った。ついに平八郎は暴挙にでて,政府や民間の蔵を打ち壊して一時の救済に充てることにした。』大阪城誌(小野清,1899)とある。
この『仕事に就くことも,食べることも簡単ではない』の原文が【業ノ手ニ執ル可キ無ク、食ノ口ニ糊ス可キ無ク】である。
私財をなげうって庶民のために尽くす。(反逆者の汚名を着ることになっても)
このような義臣のいたことを誇りに思う。
渡りを禁ずる,このたびの公務員改革は明治以来の快挙という。
できればもう少し遡って天保の義臣を顕彰して欲しいものだ。
さて,その語源となった言葉は史記にある。
「伍子胥(ごししょ)は,夜歩き昼は隠れて,陵水にいたる。口に糊することなく..呉に到着し,闔閭(こうりょ)をその王とした」(史記)
伍子胥は孫武(そんぶ:孫子の兵法の著者)と共に闔閭を補佐し,楚の首都を陥落し,闔閭は斉桓公,晋文公,楚荘王に続く,春秋の覇者となった。
----------------------------------------------------------------------------------------------
【伍子胥橐載而出昭關,夜行晝伏,至於陵水,無以糊其口,厀行蒲伏,稽首肉袒,鼓腹吹篪,乞食於吳市,卒興吳國,闔閭為伯。】史記范睢蔡澤列傳
2009年02月03日
(お)鬼(おに)
「お父さん,みんなが『鬼は外,福は内』ってやったら,お外は鬼さんばっかりになっちゃうね。」
今日は節分である。
恵方巻の起源は,昭和7年頃の大阪の鮨屋のようである。
割と新しい風習だ。
豆まきの起源は相当古い。
始まりは,奈良時代とも室町時代とも言われているようであるが,
秦の始皇帝が送り出した徐福が伝えたという伝説を読んだことがある。
だから,『福は内』なのかと妙に納得した覚えがある。
もしそれが事実だとすれば,2200年前である。
春秋(紀元前770-紀元前476年)の周礼に
「大鬼を祀るときは..豆をたかつきに入れてすすめる。」
とある。決してぶつけられたりはしていない。
信仰の対象から魔もの扱いに変わって,鬼も赤くなったり青くなったりと大変だろう。
明日は立春,季節は春である。しかし,年を越した気はまだない。
豆ならぬ,票目当ての定額給付金や利権がらみのODAのばらまきに,
国民の方が赤くなったり青くなったりだ。
------------------------------------------------------------------------------------
【凡祀大神、享大鬼、祭大示,帥執事而卜日,宿,視滌濯,蒞玉鬯,省牲、鑊,奉玉粢,詔大號,治其大禮,詔相王之大禮。若王不與祭祀,則攝位。凡大祭祀,王后不與,則攝而薦豆籩,徹。】周禮春官宗伯
今日は節分である。
恵方巻の起源は,昭和7年頃の大阪の鮨屋のようである。
割と新しい風習だ。
豆まきの起源は相当古い。
始まりは,奈良時代とも室町時代とも言われているようであるが,
秦の始皇帝が送り出した徐福が伝えたという伝説を読んだことがある。
だから,『福は内』なのかと妙に納得した覚えがある。
もしそれが事実だとすれば,2200年前である。
春秋(紀元前770-紀元前476年)の周礼に
「大鬼を祀るときは..豆をたかつきに入れてすすめる。」
とある。決してぶつけられたりはしていない。
信仰の対象から魔もの扱いに変わって,鬼も赤くなったり青くなったりと大変だろう。
明日は立春,季節は春である。しかし,年を越した気はまだない。
豆ならぬ,票目当ての定額給付金や利権がらみのODAのばらまきに,
国民の方が赤くなったり青くなったりだ。
------------------------------------------------------------------------------------
【凡祀大神、享大鬼、祭大示,帥執事而卜日,宿,視滌濯,蒞玉鬯,省牲、鑊,奉玉粢,詔大號,治其大禮,詔相王之大禮。若王不與祭祀,則攝位。凡大祭祀,王后不與,則攝而薦豆籩,徹。】周禮春官宗伯
2009年02月02日
(の)嚢中の錐
「天才は元来嚢中の錐のようなもので,どの道へ入っても必ず現れてくる」
嚢中の錐(のうちゅうのきり):すぐれた人物は,多くの人の中にあってもその才能によって目立って見えることのたとえ。才能のある者は隠れていても頭角をあらわすということ。袋の中に入れた錐の先端は,おのずと布を突き抜けて外に出ることから。出典:史記
(新明解故事ことわざ辞典)
史記の故事は次のようである。
『楚との困難な交渉に迫られた趙の平原君(へいげんくん)は,随行させる人選に悩んでいた。平原君はその役目に自薦してきた毛遂(もうつい)に言った。
「賢士というものは,たとえば錐(きり)が嚢(ふくろ)の中にあるようなもので,必ず頭角を現すと言います。先生は私のところへ来られて3年経つがそのように目立ったことがありませんね。」
毛遂は答えた。
「袋の話は今日初めて聞きました。もし嚢に入れてもらえればそのようにいたしましょう。」
...こうして交渉団に加わった毛遂は,命がけの交渉を行って,交渉を成功させた。』
毛遂は,平原君の食客であった。数千人いると言われた食客の中で,頭角を現すのは難しかったようである。
3年も居るのに..などと嫌味を言われている。
困難な仕事,人の嫌がる仕事を率先して行って初めて認められるということなのか。
しかし,なぜ袋に錐をしまうのだろうか。例としているからにはそのような習慣があったのだろうか。
ざっと調べてみたが,錐は「立錐の余地なし」など錐の先を立てるほどのすきまもない「狭さ」や「見識の小ささ」に用いられており,この例のような「能力の高さ」としての意味には使われていない。
すると,元々の意味は「小さな袋の中では,さらに能力を発揮する余地はない」との論理になる。
(これはあくまで仮説であるが)
『普段でも目立ったところがなかったのに,このような困難な仕事のチームに抜擢してもらおうなんて,虫がよすぎるんじゃないか?』というさらに厳しい評価だったことになる。
--------------------------------------------------------------------------------------------------
【平原君曰:“夫賢士之處世也,譬若錐之處囊中,其末立見。今先生處勝之門下三年於此矣,左右未有所稱誦,勝未有所聞,是先生無所有也。先生不能,先生留。”毛遂曰:“臣乃今日請處囊中耳。使遂蚤得處囊中,乃穎脫而出,非特其末見而已。”平原君竟與毛遂偕。十九人相與目笑之而未廢也。】史記平原君虞卿列傳
嚢中の錐(のうちゅうのきり):すぐれた人物は,多くの人の中にあってもその才能によって目立って見えることのたとえ。才能のある者は隠れていても頭角をあらわすということ。袋の中に入れた錐の先端は,おのずと布を突き抜けて外に出ることから。出典:史記
(新明解故事ことわざ辞典)
史記の故事は次のようである。
『楚との困難な交渉に迫られた趙の平原君(へいげんくん)は,随行させる人選に悩んでいた。平原君はその役目に自薦してきた毛遂(もうつい)に言った。
「賢士というものは,たとえば錐(きり)が嚢(ふくろ)の中にあるようなもので,必ず頭角を現すと言います。先生は私のところへ来られて3年経つがそのように目立ったことがありませんね。」
毛遂は答えた。
「袋の話は今日初めて聞きました。もし嚢に入れてもらえればそのようにいたしましょう。」
...こうして交渉団に加わった毛遂は,命がけの交渉を行って,交渉を成功させた。』
毛遂は,平原君の食客であった。数千人いると言われた食客の中で,頭角を現すのは難しかったようである。
3年も居るのに..などと嫌味を言われている。
困難な仕事,人の嫌がる仕事を率先して行って初めて認められるということなのか。
しかし,なぜ袋に錐をしまうのだろうか。例としているからにはそのような習慣があったのだろうか。
ざっと調べてみたが,錐は「立錐の余地なし」など錐の先を立てるほどのすきまもない「狭さ」や「見識の小ささ」に用いられており,この例のような「能力の高さ」としての意味には使われていない。
すると,元々の意味は「小さな袋の中では,さらに能力を発揮する余地はない」との論理になる。
(これはあくまで仮説であるが)
『普段でも目立ったところがなかったのに,このような困難な仕事のチームに抜擢してもらおうなんて,虫がよすぎるんじゃないか?』というさらに厳しい評価だったことになる。
--------------------------------------------------------------------------------------------------
【平原君曰:“夫賢士之處世也,譬若錐之處囊中,其末立見。今先生處勝之門下三年於此矣,左右未有所稱誦,勝未有所聞,是先生無所有也。先生不能,先生留。”毛遂曰:“臣乃今日請處囊中耳。使遂蚤得處囊中,乃穎脫而出,非特其末見而已。”平原君竟與毛遂偕。十九人相與目笑之而未廢也。】史記平原君虞卿列傳
2009年02月01日
(ゐ)石に漱(くちすす)ぎ流れに枕(まくら)す
「石に漱(くちすす)ぎ流れに枕(まくら)すというか,『誤解を与えたのなら謝る』って強弁じゃないか?誤解を何も解いてないし,謝ってもいない。」
石に漱ぎ流れに枕す(いしにくちすすぎながれにまくらす):
負け惜しみが強いこと。無理にこじつけて自分の説を通すこと。
『晋(しん)の孫楚(そんそ)が,本来なら「石に枕し流れに漱ぐ(田舎に引退する意)」と言うべきところを,うっかり「石に漱ぎ流れに枕す」と言い誤まってしまったとき,「石に漱ぐ」のは歯を磨くためであり,「流れに枕する」のは俗事を聞いて汚れた耳を洗うためだとこじつけた。』(晋書)。
「夏目漱石」という号は,これに由来する。
(新明解故事ことわざ辞典)
こじつけにしてもうまく言い逃れしたものだ。
(残念ながら,これ以上の言い逃れは思い浮かばない)
ところで「枕レ石」と「漱レ流」はなぜ,田舎の象徴なのか。
「石枕」は頭がひんやりするためか俳句の6月の季語になっているようだ。
「草枕」もあって,こちらは万葉集にも出てくる「旅」のずばり「枕」言葉である。
なるほど「都落ち」のイメージがわいてくる。
では,都では何を使って「漱いでいた」のだろうか。
「・・子婦以外の者は,一番鶏が泣いたら起きだして,盥(たらい)の水で漱ぎ,枕と竹のむしろを片付け,堂と庭を掃除して,其々の仕事に付くこと」(禮記)
盥(たらい)に入った水か,なるほど。いろいろ役目が書かれてある。
では,子婦は何をするのだろう?
「父母の世話をする子」「舅と姑の世話をする嫁」「未成年の男女」..
みんな一番鶏と同時に起きて漱ぎ,髪の形や持ち物や食べ物まで決まっているようだ。
儒教の「礼」というものは精密で厳格で,社会はすべてそれに従って動いているようである。
ところが,不思議なことにこれらの人は枕とむしろを片づけない。
ここからは想像である。
枕やむしろを使う,あるいは片付けさせられるのは,下僕のような抑圧された人ということである。
それが「石に枕し流れに漱ぐ」のは,
片付ける必要がない,つまりその身分から解放されることを示す。さらに言えば,
「石に漱ぎ流れに枕す」のは,そのような身分制度そのものを否定した,完全な自由である。
しかし,その表現は,礼という常識に憑(と)りつかれている人間には理解されなかった。
だからとっさに,彼らにも解る論理でこじつけたのだ。
夏目漱石の「草枕」は,こう始まる
『..智に働けば角が立つ。情に棹せば流される。 意地を通せば窮屈だ。兎角にこの世は住みにくい。..』
そこから言葉を借りれば,
「むきになって本心を吐き出して窮屈になるより,兎角(=有り得ないこと)にしておこう」
そういう声にならない叫びが聞こえてくるのである。
----------------------------------------------------------------------------------------
【孫子荊、年少時欲隱、語王武子、當枕石漱流、誤曰、漱石枕流。王曰、流可枕、石可漱乎。孫曰、所以枕流、欲洗其耳。所以漱石、欲礪其齒。】 -- 劉義慶『世説新語』「排調第二十五」 。(Wikiquote)
【子事父母,雞初鳴,咸盥漱,櫛縰笄總,拂髦冠緌纓,端韠紳,搢笏。左右佩用,左佩紛帨、刀、礪、小觿、金燧,右佩玦、捍、管、遰、大觿、木燧,偪,屨著綦。
婦事舅姑,如事父母。雞初鳴,咸盥漱,櫛縰,笄總,衣紳。左佩紛帨、刀、礪、小觿、金燧,右佩箴、管、線、纊,施縏帙,大觿、木燧、衿纓,綦屨。 ...
男女未冠笄者,雞初鳴,咸盥漱,櫛縰,拂髦總角,衿纓,皆佩容臭,昧爽而朝,問何食飲矣。若已食則退,若未食則佐長者視具。
凡內外,雞初鳴,咸盥漱,衣服,斂枕簟,灑掃室堂及庭,布席,各從其事。 】禮記內則
石に漱ぎ流れに枕す(いしにくちすすぎながれにまくらす):
負け惜しみが強いこと。無理にこじつけて自分の説を通すこと。
『晋(しん)の孫楚(そんそ)が,本来なら「石に枕し流れに漱ぐ(田舎に引退する意)」と言うべきところを,うっかり「石に漱ぎ流れに枕す」と言い誤まってしまったとき,「石に漱ぐ」のは歯を磨くためであり,「流れに枕する」のは俗事を聞いて汚れた耳を洗うためだとこじつけた。』(晋書)。
「夏目漱石」という号は,これに由来する。
(新明解故事ことわざ辞典)
こじつけにしてもうまく言い逃れしたものだ。
(残念ながら,これ以上の言い逃れは思い浮かばない)
ところで「枕レ石」と「漱レ流」はなぜ,田舎の象徴なのか。
「石枕」は頭がひんやりするためか俳句の6月の季語になっているようだ。
「草枕」もあって,こちらは万葉集にも出てくる「旅」のずばり「枕」言葉である。
なるほど「都落ち」のイメージがわいてくる。
では,都では何を使って「漱いでいた」のだろうか。
「・・子婦以外の者は,一番鶏が泣いたら起きだして,盥(たらい)の水で漱ぎ,枕と竹のむしろを片付け,堂と庭を掃除して,其々の仕事に付くこと」(禮記)
盥(たらい)に入った水か,なるほど。いろいろ役目が書かれてある。
では,子婦は何をするのだろう?
「父母の世話をする子」「舅と姑の世話をする嫁」「未成年の男女」..
みんな一番鶏と同時に起きて漱ぎ,髪の形や持ち物や食べ物まで決まっているようだ。
儒教の「礼」というものは精密で厳格で,社会はすべてそれに従って動いているようである。
ところが,不思議なことにこれらの人は枕とむしろを片づけない。
ここからは想像である。
枕やむしろを使う,あるいは片付けさせられるのは,下僕のような抑圧された人ということである。
それが「石に枕し流れに漱ぐ」のは,
片付ける必要がない,つまりその身分から解放されることを示す。さらに言えば,
「石に漱ぎ流れに枕す」のは,そのような身分制度そのものを否定した,完全な自由である。
しかし,その表現は,礼という常識に憑(と)りつかれている人間には理解されなかった。
だからとっさに,彼らにも解る論理でこじつけたのだ。
夏目漱石の「草枕」は,こう始まる
『..智に働けば角が立つ。情に棹せば流される。 意地を通せば窮屈だ。兎角にこの世は住みにくい。..』
そこから言葉を借りれば,
「むきになって本心を吐き出して窮屈になるより,兎角(=有り得ないこと)にしておこう」
そういう声にならない叫びが聞こえてくるのである。
----------------------------------------------------------------------------------------
【孫子荊、年少時欲隱、語王武子、當枕石漱流、誤曰、漱石枕流。王曰、流可枕、石可漱乎。孫曰、所以枕流、欲洗其耳。所以漱石、欲礪其齒。】 -- 劉義慶『世説新語』「排調第二十五」 。(Wikiquote)
【子事父母,雞初鳴,咸盥漱,櫛縰笄總,拂髦冠緌纓,端韠紳,搢笏。左右佩用,左佩紛帨、刀、礪、小觿、金燧,右佩玦、捍、管、遰、大觿、木燧,偪,屨著綦。
婦事舅姑,如事父母。雞初鳴,咸盥漱,櫛縰,笄總,衣紳。左佩紛帨、刀、礪、小觿、金燧,右佩箴、管、線、纊,施縏帙,大觿、木燧、衿纓,綦屨。 ...
男女未冠笄者,雞初鳴,咸盥漱,櫛縰,拂髦總角,衿纓,皆佩容臭,昧爽而朝,問何食飲矣。若已食則退,若未食則佐長者視具。
凡內外,雞初鳴,咸盥漱,衣服,斂枕簟,灑掃室堂及庭,布席,各從其事。 】禮記內則
2009年01月31日
(う)烏合の衆
「政治理念はおかまいなしに,与党か野党かで決めるなんてまさに烏合(うごう)の衆・議員だ。」
烏合の衆(うごうのしゅう):ただ寄り集まって騒ぐだけで,統制も規律もない群衆,または軍勢のたとえ。鳥の中でも烏(からす)の群れは,寄り集まって騒ぐだけで,統制も規律もないところから。
出典:後漢書(新明解故事ことわざ辞典)
カラスは人の顔を覚えたり,自販機を使えたり,と賢い鳥である。
さらには「烏に反哺(はんぽ)の孝あり」とかなかなか親孝行である。
出来の悪い人間共と一緒にされたらカラスの沽券(こけん)にかかわる問題だ。
「烏合」で検索してみると,東觀漢記で1回,後漢書4回で使われている。
後漢書の1回は東觀漢記の引用と思われる同一の文があった。
つごう4文が「烏合」が初期に使われたと思われる文である。
不思議なことにすべてが「烏合之眾」の形で使われている。
4文を解釈してみる。
①烏合之眾をはしらせて,馬にまたがり敵に突き進み,向う所をたちまち平げた。
②漢が起こり,悪賢い烏合之眾を追い払って,天下の隅々から追い払った。
③騎兵をもちいて烏合之眾をふみにじり,くさった木を折るようにたやすく降伏させた。
④王郎は,烏合之眾を集めてはしらせ,遂に燕と趙の地を脅かした。
どうも「烏合之眾」は戦争に関係する集団のようである。
そして,「烏合」(カラスのあつまり)の眾ではなく,いきなり「烏合之眾」の一語で使われている。
「烏合之眾」は,単なる人の寄せ集めではなく,
戦争を行う訓練された統制のとれた集団だったのではないだろうか?
たとえば,日本の戦国時代の鉄砲で武装した根来衆や
秀吉に仕えた御伽衆のような職能集団ではなかったか。
ではどこの国の軍隊だったのか?
漢が成立する当時に,敵対する集団であったのだから項羽の軍団と考えるのが素直である。
つまり,本当は「(項)羽に合わさった集団」と言いたかったのだ。
だが,実名を使うのをはばかって発音の似た「烏」としたのではないか。
あるいは,さらにそこに蔑みの意味も込めているのではないだろうか。
その後,王郎の反乱の際に,敵対する軍隊の意味として「烏合之眾」を使った。
それから次第にカラスの印象だけが強まって現在の意味になった。
...これでカラスの濡れ衣も晴れるであろう。
生ゴミを漁っているカラスよりも,選挙準備に汲々とする政治家のほうがさもしく見える。
一所懸命さが見えないのだ。
----------------------------------------------------------------------------------------------
【今東帝無尺寸之柄,驅烏合之眾,跨馬陷敵,所向輒平。】東觀漢記載記公孫述
【漢起,驅輕黠烏合之眾,不當天下萬分之一,而旌旃之所撝及,書文之所通被,莫不折戈頓顙,爭受職命。】後漢書劉玄劉盆子列傳
【今東帝無尺土之柄,驅烏合之眾,跨馬陷敵,所向輒平。】後漢書隗囂公孫述列傳
【我至長安,與國家陳漁陽、上谷兵馬之用,還出太原、代郡,反覆數十日,歸發突騎以轔烏合之眾,如摧枯折腐耳。】後漢書耿弇列傳
【又卜者王郎,假名因埶,驅集烏合之眾,遂震燕、趙之地。】後漢書任李萬邳劉耿列傳
烏合の衆(うごうのしゅう):ただ寄り集まって騒ぐだけで,統制も規律もない群衆,または軍勢のたとえ。鳥の中でも烏(からす)の群れは,寄り集まって騒ぐだけで,統制も規律もないところから。
出典:後漢書(新明解故事ことわざ辞典)
カラスは人の顔を覚えたり,自販機を使えたり,と賢い鳥である。
さらには「烏に反哺(はんぽ)の孝あり」とかなかなか親孝行である。
出来の悪い人間共と一緒にされたらカラスの沽券(こけん)にかかわる問題だ。
「烏合」で検索してみると,東觀漢記で1回,後漢書4回で使われている。
後漢書の1回は東觀漢記の引用と思われる同一の文があった。
つごう4文が「烏合」が初期に使われたと思われる文である。
不思議なことにすべてが「烏合之眾」の形で使われている。
4文を解釈してみる。
①烏合之眾をはしらせて,馬にまたがり敵に突き進み,向う所をたちまち平げた。
②漢が起こり,悪賢い烏合之眾を追い払って,天下の隅々から追い払った。
③騎兵をもちいて烏合之眾をふみにじり,くさった木を折るようにたやすく降伏させた。
④王郎は,烏合之眾を集めてはしらせ,遂に燕と趙の地を脅かした。
どうも「烏合之眾」は戦争に関係する集団のようである。
そして,「烏合」(カラスのあつまり)の眾ではなく,いきなり「烏合之眾」の一語で使われている。
「烏合之眾」は,単なる人の寄せ集めではなく,
戦争を行う訓練された統制のとれた集団だったのではないだろうか?
たとえば,日本の戦国時代の鉄砲で武装した根来衆や
秀吉に仕えた御伽衆のような職能集団ではなかったか。
ではどこの国の軍隊だったのか?
漢が成立する当時に,敵対する集団であったのだから項羽の軍団と考えるのが素直である。
つまり,本当は「(項)羽に合わさった集団」と言いたかったのだ。
だが,実名を使うのをはばかって発音の似た「烏」としたのではないか。
あるいは,さらにそこに蔑みの意味も込めているのではないだろうか。
その後,王郎の反乱の際に,敵対する軍隊の意味として「烏合之眾」を使った。
それから次第にカラスの印象だけが強まって現在の意味になった。
...これでカラスの濡れ衣も晴れるであろう。
生ゴミを漁っているカラスよりも,選挙準備に汲々とする政治家のほうがさもしく見える。
一所懸命さが見えないのだ。
----------------------------------------------------------------------------------------------
【今東帝無尺寸之柄,驅烏合之眾,跨馬陷敵,所向輒平。】東觀漢記載記公孫述
【漢起,驅輕黠烏合之眾,不當天下萬分之一,而旌旃之所撝及,書文之所通被,莫不折戈頓顙,爭受職命。】後漢書劉玄劉盆子列傳
【今東帝無尺土之柄,驅烏合之眾,跨馬陷敵,所向輒平。】後漢書隗囂公孫述列傳
【我至長安,與國家陳漁陽、上谷兵馬之用,還出太原、代郡,反覆數十日,歸發突騎以轔烏合之眾,如摧枯折腐耳。】後漢書耿弇列傳
【又卜者王郎,假名因埶,驅集烏合之眾,遂震燕、趙之地。】後漢書任李萬邳劉耿列傳