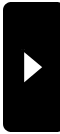2009年01月26日
(つ)恙無し(つつがなし)
「日出ずる處の天子、書を日沒する處の天子に致す。恙無きや」
聖徳太子が隋の煬帝に宛てた親書の一節である。
恙無し(つつがなし):→無恙(むよう),心配がない。病気がない。無事である。(新字源)
『無恙』を書籍で拾ってみると,諸子百家では,春秋戦国時代には見つからず漢(前207年)以後9回出現している。史記(前109年-前91年)では11回出現し,それ以降よく出現している。多くは健康であることあるいはその問いかけとして用いられており,その対象は帝・王・諸侯から実母・実子にいたるまで広く用いられている。
日本に関連する記録では,例文での出現が初めてである。(607年)聖徳太子が遣隋使に託した親書を見て,隋の煬帝は不機嫌になった。(隋書倭国伝)この時点では我が国はまだ『倭』であり『日本』という国名は使われていない。
後漢時代に「東夷倭奴国(やばんでちいさい?)」と呼んでいた国から対等に「元気ですか?」と聞かれてピクリとくるのも無理はない。617年以降隋が唐に代わっ時点でも『倭』であったが,太子の行った冠位十二階などには一定の評価を与えている。その後『倭』は『日本』という名前に変えたとなっている。(旧唐書倭国・日本国伝)
改名の理由は3つあったと言われている。
1.日の出るところにあるから。
2.倭国では雅さがなかった。
3.もともと日本という小国がありそれが倭国を征服した。
何れにしても国名を定めるに至った重要な一文であることには間違いない。
さて,現在の日本国に元気がないのはなぜか?省エネ・バイオ・ロボット..環境や医療・介護に貢献できる優秀な技術が沢山ある。物理学・化学,基礎的な研究でもノーベル賞を独り占めするほどである。国家の十分な支援もなくてよくやっている,というのが正直な感想である。
緊急経済対策の内容をみても,栄養失調と睡眠不足でフラフラの人間にダイエットや筋トレを勧めているようなイメージである。そのくせ,運動不足と飽食で贅肉たっぷりの人間にさらに栄養剤を注射しようとしている。元気ですか?と労わる代わりにこう問いかけよう,正気ですか?
【大業三年、其王多利思比孤遣使朝貢。使者曰:「聞海西菩薩天子重興佛法、故遣朝拜、兼沙門數十人來學佛法。」其國書曰「日出處天子致書日沒處天子無恙」云云。帝覽之不悅、謂鴻臚卿曰:「蠻夷書有無禮者、勿復以聞。】隋書倭国伝
【倭國者、古倭奴國也。去京師一萬四千里、在新羅東南大海中、依山島而居。東西五月行、南北三月行。世與中國通。其國、居無城郭、以木為柵、以草為屋。四面小島五十餘國、皆附屬焉。其王姓阿毎氏、置一大率、檢察諸國、皆畏附之。設官有十二等。】旧唐書倭国・日本国伝
【日本國者、倭國之別種也。以其國在日邊、故以日本為名。或曰:倭國自惡其名不雅、改為日本。或云:日本舊小國、併倭國之地。其人入朝者、多自矜大、不以實對、故中國疑焉。又云:其國界東西南北各數千里、西界、南界咸至大海、東界、北界有大山為限、山外即毛人之國。】旧唐書倭国・日本国伝
聖徳太子が隋の煬帝に宛てた親書の一節である。
恙無し(つつがなし):→無恙(むよう),心配がない。病気がない。無事である。(新字源)
『無恙』を書籍で拾ってみると,諸子百家では,春秋戦国時代には見つからず漢(前207年)以後9回出現している。史記(前109年-前91年)では11回出現し,それ以降よく出現している。多くは健康であることあるいはその問いかけとして用いられており,その対象は帝・王・諸侯から実母・実子にいたるまで広く用いられている。
日本に関連する記録では,例文での出現が初めてである。(607年)聖徳太子が遣隋使に託した親書を見て,隋の煬帝は不機嫌になった。(隋書倭国伝)この時点では我が国はまだ『倭』であり『日本』という国名は使われていない。
後漢時代に「東夷倭奴国(やばんでちいさい?)」と呼んでいた国から対等に「元気ですか?」と聞かれてピクリとくるのも無理はない。617年以降隋が唐に代わっ時点でも『倭』であったが,太子の行った冠位十二階などには一定の評価を与えている。その後『倭』は『日本』という名前に変えたとなっている。(旧唐書倭国・日本国伝)
改名の理由は3つあったと言われている。
1.日の出るところにあるから。
2.倭国では雅さがなかった。
3.もともと日本という小国がありそれが倭国を征服した。
何れにしても国名を定めるに至った重要な一文であることには間違いない。
さて,現在の日本国に元気がないのはなぜか?省エネ・バイオ・ロボット..環境や医療・介護に貢献できる優秀な技術が沢山ある。物理学・化学,基礎的な研究でもノーベル賞を独り占めするほどである。国家の十分な支援もなくてよくやっている,というのが正直な感想である。
緊急経済対策の内容をみても,栄養失調と睡眠不足でフラフラの人間にダイエットや筋トレを勧めているようなイメージである。そのくせ,運動不足と飽食で贅肉たっぷりの人間にさらに栄養剤を注射しようとしている。元気ですか?と労わる代わりにこう問いかけよう,正気ですか?
【大業三年、其王多利思比孤遣使朝貢。使者曰:「聞海西菩薩天子重興佛法、故遣朝拜、兼沙門數十人來學佛法。」其國書曰「日出處天子致書日沒處天子無恙」云云。帝覽之不悅、謂鴻臚卿曰:「蠻夷書有無禮者、勿復以聞。】隋書倭国伝
【倭國者、古倭奴國也。去京師一萬四千里、在新羅東南大海中、依山島而居。東西五月行、南北三月行。世與中國通。其國、居無城郭、以木為柵、以草為屋。四面小島五十餘國、皆附屬焉。其王姓阿毎氏、置一大率、檢察諸國、皆畏附之。設官有十二等。】旧唐書倭国・日本国伝
【日本國者、倭國之別種也。以其國在日邊、故以日本為名。或曰:倭國自惡其名不雅、改為日本。或云:日本舊小國、併倭國之地。其人入朝者、多自矜大、不以實對、故中國疑焉。又云:其國界東西南北各數千里、西界、南界咸至大海、東界、北界有大山為限、山外即毛人之國。】旧唐書倭国・日本国伝
2009年01月25日
(そ)双璧
「浅田真央と安藤美姫は日本フィギュアスケート界の双璧だね」と使う。どちらも美しく,見る者に感動と勇気を与えてくれる日本の至宝である。
双璧(そうへき):一対の宝玉の意で,優劣をつけられない二つの優れたもの,または人のたとえ。『陸凱の子の暐(い)と弟の恭之(きょうし)とは,二人とも秀才としての名声が高かった。..賈禎はこの兄弟に会い,感嘆して,私は長生きしたので一対の立派な宝玉を見た,と言った』出典北史(新明解故事ことわざ辞典)
春秋時代の宝玉といえば「垂棘の璧(すいきょくのへき)」と「和氏の璧(かしのたま)」が文字通りの双璧である。諸子百家以降多くの書籍に登場し,故事成語にもなっている。
垂棘(すいきょく):晋の玉の産地
和氏(かし):卞和,荊の人
「垂棘の璧」は故事成語『小利は大利の残い(しょうりはだいりのそこない)』に登場する。
晋の献公が虢(かく)を伐つためには,まず虢と友好関係にある虞(ぐ)を通過しなければならない。そこで荀息の献策により晋代々の宝玉である垂棘の璧と屈産の馬を虞公に贈って,通過の安全を確保した。荀息は虢を滅ぼし,そのあと後ろ盾を失った虞を易々と滅ぼし,璧と馬をまんまと取り返した。(韓非子十過)
「和氏の璧」は故事成語になっている。
楚の和氏が山中で得た宝玉の原石を厲王に献上したところ,ただの石であると鑑定され罰として左足を切られた。次の武王の代になって再び献上したところ,また石だと鑑定されて右足を切られた。次の文王の代になって,今度は命を取られると血の涙を流した和氏であったが,磨いてみたところすばらしい宝玉になった。(韓非子和氏)なお,楚→荊,文王→共王としたもの。(新序雜事五)
和氏の璧には後日譚があり,『完璧』,『刎頸の交わり』の故事を生むが,これは別稿にゆずる。
時代はずっと下って三国時代,魏の文帝となった曹丕はこのように言っている。
『宝玉は君子の徳のようなものだと言われている。晉の垂棘,魯の璵璠,宋の結綠,楚の和璞の価値は万金を越え,貴重さは都城ほどである。私は四宝を見たことがなく自分には徳がないことも分かっているが,欲しくて憧れている。..』
まだあと二つあるのか。
宝は人の心を惑わし,欲望は城や国さえも失うことを厭わない。そして戦争や犯罪を引き起こすのである。『財宝は天に積め(マタイ伝第6章20)』とは国や宗教の違いを超えて,苦難の末に手に入れた知恵という至宝であろう。
さて,2000年後,世界中で宝への欲望はとどまるところを知らず,悪知恵を働かせる者が後を絶たない。紛争・麻薬・偽造・強盗・詐欺..政治の腐敗が彼らの動きをさらに活気づけている。民に帰すべき宝を国家が壟断してることが根本的な問題なのだ。
日本の例でいえば省利省益に走る官僚とその傀儡となった族議員,業界団体であろう。彼らが求めているものは璧によく似て非なる壁(かべ)であろう。国益の専横を保つ省壁である。このような壁は一つでたくさんであるし,必ず破壊せねばならぬ。
【昔者晉獻公欲假道於虞以伐虢。荀息曰:“君其以垂棘之璧、與屈產之乘,賂虞公,求假道焉,必假我道。”君曰:“垂棘之璧,吾先君之寶也;屈產之乘,寡人之駿馬也。..夫虞之有虢也,如車之有輔,輔依車,車亦依輔,虞、虢之勢正是也。若假之道,則虢朝亡而虞夕從之矣。不可,願勿許。”虞公弗聽,遂假之道。荀息伐虢之,還反處三年,興兵伐虞,又剋之。荀息牽馬操璧而報獻公,獻公說曰:“璧則猶是也。雖然,馬齒亦益長矣。”故虞公之兵殆而地削者何也?愛小利而不慮其害。故曰:顧小利則大利之殘也。】韓非子十過
【楚人和氏得玉璞楚山中,奉而獻之厲王,厲王使玉人相之,玉人曰:“石也。”王以和為誑,而刖其左足。及厲王薨,武王即位,和又奉其璞而獻之武王,武王使玉人相之,又曰“石也”,王又以和為誑,而刖其右足。武王薨,文王即位,和乃抱其璞而哭於楚山之下,三日三夜,泣盡而繼之以血。王聞之,使人問其故,曰:“天下之刖者多矣,子奚哭之悲也?”和曰:“吾非悲刖也,悲夫寶玉而題之以石,貞士而名之以誑,此吾所以悲也。”王乃使玉人理其璞而得寶焉,遂命曰:“和氏之璧。”】韓非子和氏
双璧(そうへき):一対の宝玉の意で,優劣をつけられない二つの優れたもの,または人のたとえ。『陸凱の子の暐(い)と弟の恭之(きょうし)とは,二人とも秀才としての名声が高かった。..賈禎はこの兄弟に会い,感嘆して,私は長生きしたので一対の立派な宝玉を見た,と言った』出典北史(新明解故事ことわざ辞典)
春秋時代の宝玉といえば「垂棘の璧(すいきょくのへき)」と「和氏の璧(かしのたま)」が文字通りの双璧である。諸子百家以降多くの書籍に登場し,故事成語にもなっている。
垂棘(すいきょく):晋の玉の産地
和氏(かし):卞和,荊の人
「垂棘の璧」は故事成語『小利は大利の残い(しょうりはだいりのそこない)』に登場する。
晋の献公が虢(かく)を伐つためには,まず虢と友好関係にある虞(ぐ)を通過しなければならない。そこで荀息の献策により晋代々の宝玉である垂棘の璧と屈産の馬を虞公に贈って,通過の安全を確保した。荀息は虢を滅ぼし,そのあと後ろ盾を失った虞を易々と滅ぼし,璧と馬をまんまと取り返した。(韓非子十過)
「和氏の璧」は故事成語になっている。
楚の和氏が山中で得た宝玉の原石を厲王に献上したところ,ただの石であると鑑定され罰として左足を切られた。次の武王の代になって再び献上したところ,また石だと鑑定されて右足を切られた。次の文王の代になって,今度は命を取られると血の涙を流した和氏であったが,磨いてみたところすばらしい宝玉になった。(韓非子和氏)なお,楚→荊,文王→共王としたもの。(新序雜事五)
和氏の璧には後日譚があり,『完璧』,『刎頸の交わり』の故事を生むが,これは別稿にゆずる。
時代はずっと下って三国時代,魏の文帝となった曹丕はこのように言っている。
『宝玉は君子の徳のようなものだと言われている。晉の垂棘,魯の璵璠,宋の結綠,楚の和璞の価値は万金を越え,貴重さは都城ほどである。私は四宝を見たことがなく自分には徳がないことも分かっているが,欲しくて憧れている。..』
まだあと二つあるのか。
宝は人の心を惑わし,欲望は城や国さえも失うことを厭わない。そして戦争や犯罪を引き起こすのである。『財宝は天に積め(マタイ伝第6章20)』とは国や宗教の違いを超えて,苦難の末に手に入れた知恵という至宝であろう。
さて,2000年後,世界中で宝への欲望はとどまるところを知らず,悪知恵を働かせる者が後を絶たない。紛争・麻薬・偽造・強盗・詐欺..政治の腐敗が彼らの動きをさらに活気づけている。民に帰すべき宝を国家が壟断してることが根本的な問題なのだ。
日本の例でいえば省利省益に走る官僚とその傀儡となった族議員,業界団体であろう。彼らが求めているものは璧によく似て非なる壁(かべ)であろう。国益の専横を保つ省壁である。このような壁は一つでたくさんであるし,必ず破壊せねばならぬ。
【昔者晉獻公欲假道於虞以伐虢。荀息曰:“君其以垂棘之璧、與屈產之乘,賂虞公,求假道焉,必假我道。”君曰:“垂棘之璧,吾先君之寶也;屈產之乘,寡人之駿馬也。..夫虞之有虢也,如車之有輔,輔依車,車亦依輔,虞、虢之勢正是也。若假之道,則虢朝亡而虞夕從之矣。不可,願勿許。”虞公弗聽,遂假之道。荀息伐虢之,還反處三年,興兵伐虞,又剋之。荀息牽馬操璧而報獻公,獻公說曰:“璧則猶是也。雖然,馬齒亦益長矣。”故虞公之兵殆而地削者何也?愛小利而不慮其害。故曰:顧小利則大利之殘也。】韓非子十過
【楚人和氏得玉璞楚山中,奉而獻之厲王,厲王使玉人相之,玉人曰:“石也。”王以和為誑,而刖其左足。及厲王薨,武王即位,和又奉其璞而獻之武王,武王使玉人相之,又曰“石也”,王又以和為誑,而刖其右足。武王薨,文王即位,和乃抱其璞而哭於楚山之下,三日三夜,泣盡而繼之以血。王聞之,使人問其故,曰:“天下之刖者多矣,子奚哭之悲也?”和曰:“吾非悲刖也,悲夫寶玉而題之以石,貞士而名之以誑,此吾所以悲也。”王乃使玉人理其璞而得寶焉,遂命曰:“和氏之璧。”】韓非子和氏
2009年01月24日
(れ)連衡(れんこう)
「総選挙の結果,比較第1党だったら小党と連衡し,第2党だったら第3党以下と合従して与党の座を守る。」というのが正しい。第1党と第2党は合従できない。
連衡(れんこう):戦国時代,張儀の主張した説で,韓・魏・趙・燕・斉・楚の六国連合(合従策)に対抗して秦がそれぞれの国と個別に同盟する策。衡は横に同じく,東西の意。六国は函谷関の東に秦は西にあったのでいう。(新字源に一部追記)
秦は,この戦略により六国の合従を解消させ各個撃破を可能とし,最後に西端の斉を滅ぼして統一を完成させた。
張儀は楚で盗人の濡れ衣を着せられ大怪我を負ったが,その際妻に舌はついているかと尋ね「舌さえついていれば大丈夫だ」と安心したという。 史記張儀列傳
さて,国会漢字検定の話題は3回目となったが,本日で打ち止めにしたい。
出題文中にでてくる故事成語は,出題された「朝令暮改」「叱咤激励」「合従連衡」「乾坤一擲」以外に「完膚無き」「奔走」「領袖」「王道」「大同」「邪道」,宗教的なものでは,「修羅」「刹那」となかなかのものである。
カタカナ語は固有名詞を除いて40語あまり,出現回数の多いものでは「リーダー」11回,「トップ」,「テーマ」各5回である。
文中に取り上げられた政治家は歴代首相を中心に18名であった。
句読点を除いて1万2千字足らずの文章であるが,盛りだくさんで読むのがつらい。
【張儀已學游說諸侯。嘗從楚相飲,已而楚相亡璧,門下意張儀,曰:“儀貧無行,必此盜相君之璧。”共執張儀,掠笞數百,不服,醳之。其妻曰:“嘻!子毋讀書游說,安得此辱乎?”張儀謂其妻曰:“視吾舌尚在不?”其妻笑曰:“舌在也。”儀曰:“足矣。”】 史記張儀列傳
連衡(れんこう):戦国時代,張儀の主張した説で,韓・魏・趙・燕・斉・楚の六国連合(合従策)に対抗して秦がそれぞれの国と個別に同盟する策。衡は横に同じく,東西の意。六国は函谷関の東に秦は西にあったのでいう。(新字源に一部追記)
秦は,この戦略により六国の合従を解消させ各個撃破を可能とし,最後に西端の斉を滅ぼして統一を完成させた。
張儀は楚で盗人の濡れ衣を着せられ大怪我を負ったが,その際妻に舌はついているかと尋ね「舌さえついていれば大丈夫だ」と安心したという。 史記張儀列傳
さて,国会漢字検定の話題は3回目となったが,本日で打ち止めにしたい。
出題文中にでてくる故事成語は,出題された「朝令暮改」「叱咤激励」「合従連衡」「乾坤一擲」以外に「完膚無き」「奔走」「領袖」「王道」「大同」「邪道」,宗教的なものでは,「修羅」「刹那」となかなかのものである。
カタカナ語は固有名詞を除いて40語あまり,出現回数の多いものでは「リーダー」11回,「トップ」,「テーマ」各5回である。
文中に取り上げられた政治家は歴代首相を中心に18名であった。
句読点を除いて1万2千字足らずの文章であるが,盛りだくさんで読むのがつらい。
【張儀已學游說諸侯。嘗從楚相飲,已而楚相亡璧,門下意張儀,曰:“儀貧無行,必此盜相君之璧。”共執張儀,掠笞數百,不服,醳之。其妻曰:“嘻!子毋讀書游說,安得此辱乎?”張儀謂其妻曰:“視吾舌尚在不?”其妻笑曰:“舌在也。”儀曰:“足矣。”】 史記張儀列傳
2009年01月23日
(た)蛇足,大同小異
「蛇足のような定額給付金を除けば,与野党の予算案は大同小異で成立は間違いないだろう」と使う。
蛇足(だそく):よけいなつけ足し。なくてもよいむだなもののこと。また,しなくてもよいことをすること。『昔,楚の国で,祠の司祭者が召使たちに大杯に盛った酒を振る舞った。召使たちは,何人もで飲むには足りないが一人で飲むには多すぎる,ひとつ地面に蛇の絵を描き,早く描き上げた者が飲むことにしようときめて同時に描き始めた。最初に描いた者が酒をひき寄せて飲もうとしながら,自分の早さを自慢して「足まで描けるぞ」と描いているうちに,もう一人の者が描き上げて杯を奪い取り「蛇に足はない,したがって酒を飲む権利はわたしにある」と言ってその酒を飲んでしまった。』出典戦国策。(新明解故事ことわざ辞典)
大同小異(だいどうしょうい):細かい部分でわずかな違いはあるが,全体としてだいたい同じであること。似たりよったり。『だいたいは同じであるが,細かい点でいくらかちがいがある,これを小同異といい,万事見方によっては皆同じであるが,見方をかえれば皆異なっている,これを大同異という』出典荘子。(新明解故事ことわざ辞典)
蛇足が本来意味するものは,蛇に足をつけてしまった愚にあるのではなく,一杯を多数で分けることの無理と受益者の決定法についての拙速を批判していることにある。同様に大同小異は,見かけの似たりよったり(小同異)ではなく,方法はひとつでも結果は見方によって異なる(大同異),という評価の限界を言っているのである。問題の本質をついた見事な故事成語である。
さて,漢字検定の続きである。尚,引用文は論理が明確になるよう適宜修正した。
『小泉元首相が進めた構造改革は,政官業の癒着を断ち切る政策であり,危機に瀕した自民党を救った中興の祖であることは論をまたない。』
>『中興の祖』は長い歴史を経て後世の人々が評する言葉である。『論をまたない』ではあるが,自民党が圧勝したこと以外に中興の祖であることを示す例は何か。
『『失われた十年』を再現させてはならない。バブル崩壊後,政党は経済再生に知恵を絞らず,永田町は政治改革政局に身を窶し,経済の崩落を水際で止めることができなかった。』
>政治改革に痩せるほどに打ち込んだのなら,国民は責めないだろう。崩壊は水際では止められない,土留,崖っぷちで止めるのだ。
『官僚が公共精神を失ったことは政権党の責任であり,その再生は行政の長(私)の責任であり,後期高齢者医療制度で国民を不安にした責任を痛感する。しかし,朝令暮改で制度を廃止するより,誤解を受けない改革を施すことが私の責任である。』
>責任ばかりで義務がない。後期高齢者医療制度は公共精神を失った官僚が作ったという論理か。それを法律『令』としたのは私であることの責任は認めていない。悪法なら正す義務があるはずだ。『改』は改革ではなく改正である。
『衆院選で勝っても衆参ねじれの混乱は続く,というシニカルな言説は,諸外国の例を知らず,国民を愚弄する悲観論である。』
>混乱が続くのは事実であってそれを不安に思うのは冷笑的で悲観的なのか?諸外国の例が示されていないが,事例を示さず断定することこそ『愚弄』である。
『総選挙で与野党が僅差となっても,大連立や再編はしない。小選挙区で競い合った党が投票結果とは別のところで合従連衡したり、離合集散を行うのは、政党政治のためにもよくない。』
>『合従連衡』は重要な戦略であるから,総選挙の前に示されるべき。政党政治ためにも..と並列されているもうひとつのよくないことは何か不明。
『総選挙が政権を賭けた民主党との乾坤一擲の戦いなのは言うまでもない。』
>天と地『乾坤』がひっくり返るような大勝負を期待したいが,『擲』はさいころを投げる意味で大連立や再編があるかもしれない博打だとしている。
『参院選で、自民党が開けた穴を賢しく狙い、疲弊する地方の不満をすくいあげた選挙戦術はさすが自民党選挙を知り抜いた小沢氏の面目躍如とは思ったが..』
>疲弊する地方の不満をすくいあげるのは選挙戦術だというのだろうか。
文章全体を見て,文字の出現回数を調べた。
多いものは,政(_治,_権,_党)148回.党(自民_,民主_)99回,国(_民,_際,_会)98回,私88回である。少ないものは,道23回,知15回,義6回,忠1回,徳と礼は0回であった。王と覇の混同も見られた。違いについては覇王を確認してください。
蛇足ではあるがリーダーの仕事は二つである。
1.判断すること
2.夢を与えること
蛇足(だそく):よけいなつけ足し。なくてもよいむだなもののこと。また,しなくてもよいことをすること。『昔,楚の国で,祠の司祭者が召使たちに大杯に盛った酒を振る舞った。召使たちは,何人もで飲むには足りないが一人で飲むには多すぎる,ひとつ地面に蛇の絵を描き,早く描き上げた者が飲むことにしようときめて同時に描き始めた。最初に描いた者が酒をひき寄せて飲もうとしながら,自分の早さを自慢して「足まで描けるぞ」と描いているうちに,もう一人の者が描き上げて杯を奪い取り「蛇に足はない,したがって酒を飲む権利はわたしにある」と言ってその酒を飲んでしまった。』出典戦国策。(新明解故事ことわざ辞典)
大同小異(だいどうしょうい):細かい部分でわずかな違いはあるが,全体としてだいたい同じであること。似たりよったり。『だいたいは同じであるが,細かい点でいくらかちがいがある,これを小同異といい,万事見方によっては皆同じであるが,見方をかえれば皆異なっている,これを大同異という』出典荘子。(新明解故事ことわざ辞典)
蛇足が本来意味するものは,蛇に足をつけてしまった愚にあるのではなく,一杯を多数で分けることの無理と受益者の決定法についての拙速を批判していることにある。同様に大同小異は,見かけの似たりよったり(小同異)ではなく,方法はひとつでも結果は見方によって異なる(大同異),という評価の限界を言っているのである。問題の本質をついた見事な故事成語である。
さて,漢字検定の続きである。尚,引用文は論理が明確になるよう適宜修正した。
『小泉元首相が進めた構造改革は,政官業の癒着を断ち切る政策であり,危機に瀕した自民党を救った中興の祖であることは論をまたない。』
>『中興の祖』は長い歴史を経て後世の人々が評する言葉である。『論をまたない』ではあるが,自民党が圧勝したこと以外に中興の祖であることを示す例は何か。
『『失われた十年』を再現させてはならない。バブル崩壊後,政党は経済再生に知恵を絞らず,永田町は政治改革政局に身を窶し,経済の崩落を水際で止めることができなかった。』
>政治改革に痩せるほどに打ち込んだのなら,国民は責めないだろう。崩壊は水際では止められない,土留,崖っぷちで止めるのだ。
『官僚が公共精神を失ったことは政権党の責任であり,その再生は行政の長(私)の責任であり,後期高齢者医療制度で国民を不安にした責任を痛感する。しかし,朝令暮改で制度を廃止するより,誤解を受けない改革を施すことが私の責任である。』
>責任ばかりで義務がない。後期高齢者医療制度は公共精神を失った官僚が作ったという論理か。それを法律『令』としたのは私であることの責任は認めていない。悪法なら正す義務があるはずだ。『改』は改革ではなく改正である。
『衆院選で勝っても衆参ねじれの混乱は続く,というシニカルな言説は,諸外国の例を知らず,国民を愚弄する悲観論である。』
>混乱が続くのは事実であってそれを不安に思うのは冷笑的で悲観的なのか?諸外国の例が示されていないが,事例を示さず断定することこそ『愚弄』である。
『総選挙で与野党が僅差となっても,大連立や再編はしない。小選挙区で競い合った党が投票結果とは別のところで合従連衡したり、離合集散を行うのは、政党政治のためにもよくない。』
>『合従連衡』は重要な戦略であるから,総選挙の前に示されるべき。政党政治ためにも..と並列されているもうひとつのよくないことは何か不明。
『総選挙が政権を賭けた民主党との乾坤一擲の戦いなのは言うまでもない。』
>天と地『乾坤』がひっくり返るような大勝負を期待したいが,『擲』はさいころを投げる意味で大連立や再編があるかもしれない博打だとしている。
『参院選で、自民党が開けた穴を賢しく狙い、疲弊する地方の不満をすくいあげた選挙戦術はさすが自民党選挙を知り抜いた小沢氏の面目躍如とは思ったが..』
>疲弊する地方の不満をすくいあげるのは選挙戦術だというのだろうか。
文章全体を見て,文字の出現回数を調べた。
多いものは,政(_治,_権,_党)148回.党(自民_,民主_)99回,国(_民,_際,_会)98回,私88回である。少ないものは,道23回,知15回,義6回,忠1回,徳と礼は0回であった。王と覇の混同も見られた。違いについては覇王を確認してください。
蛇足ではあるがリーダーの仕事は二つである。
1.判断すること
2.夢を与えること
2009年01月22日
(よ)要領を得ず
「今日の国会論戦は論点がぼやけていたのか,質問するほうも答えるほうも要領を得ずだったね」と使う。
要領を得ず(ようりょうをえず):物事のいちばん大切なところをつかんでいないたとえ。また,何が何だかよくわからないこと。出典史記(新明解故事ことわざ辞典)
国会で漢字検定が行われた。読みの問題である。(出題・解答は文末参照)しかし重要なのは意味で考えるべきなので出題文『強い日本を!私の国家再建計画』(文藝春秋2008年11月号)を読んでみた。引用文は長文で修飾語が多いため論理を整理して読み下した後,解釈を試みる。
『総裁選における7割の得票は望外であり,就中,地方での圧勝は私の宝だと思ったが所詮準決勝でしかない。』
>宝が所詮○○なしとはえらく軽いものだったらしい。そのわりにまだ決勝戦は始まっていない。
『決勝戦たる総選挙で我々が勝たなければならい。危機(=衆参のねじれ)から逃げ、あるいは唯々諾々と政権を手放せば、国の舵取りを過つことになる。』
>ねじれは国民の選択の結果であり,逃れることはできないし,逆らうこともできない。
『Japain【日本の苦悩(失われた10年)】と揶揄される日本の存在感の低下は国家に対する国民の信頼感を痛めた。』
>政治が苦悩を生み,信頼感を低下させたのである。存在感の低下が信頼感を痛めるというのは論理的でない。
『もう一度国民の審判を仰ぎたい。日本経済を再生し改革を続行する見取り図と手だてを提起するのは畢竟、そのためである。』
>国民の審判を受けるためか,日本経済を再生するためか,改革を続行するためか畢竟,目的はなんだろう。
『国民の真剣なまなざしは,衆参ねじれの危機を解決して強い政治に立ち戻れ,と希求する叱咤激励の視線だと私は思った。』>まなざしは視線に違いないが,大声は出せない。希求するのは弱い立場の者,激励するのは同位か強い立場の者である。国民の視点をどの位置に置いているのかわからない。
全部で12あるようだが,疲れたので明日に続ける。昨日は17条の憲法で涙が出てきたが,今日は欠伸しか出ない。
1.就中(なかんずく):(ナカニツクの音便)その中で。とりわけて。特に。(広辞苑)
2.唯々諾々(いいだくだく):事のよしあしにかかわらず人のことばに従うこと。「唯」は「はい」とつつしんですぐに答えることば。「諾」は「はい」とゆっくり答える。(新字源)
3.揶揄(やゆ):手をあげてからかう。あざける。「揶」からかう。あざける。「揄」①ひく②ほめそやす③からかう。なぶる。(新字源)
4.畢竟(ひっきょう):終局の意。つまり。結局。「畢」①あみ②かり③星座の名④おわる⑤つくす⑥ついに⑦ことごとく「竟」①つきる②おわる③きわめる④わたる⑤ついに。(新字源)
5.叱咤激励(しったげきれい):「叱咤」大声でしかりつける。大声でどなる。(史記淮陰侯伝)「激励」はげます。つとめはげむ。(新字源)
6.中興の祖(ちゅうこうのそ):「中興」おとろえていたのがふたたびさかんになること。「祖」④物事のもとを開いた者。(新字源)
7.窶し(やつし):「窶」まずしい。やつれる。やせおとろえる。(新字源)
8.朝令暮改(ちょうれいぼかい):→朝令暮改を見てください。
9.愚弄(ぐろう):人をばかにする。あなどってなぶりものにする。「愚」①おろか④あなどる「弄」①もてあそぶ,ほしいままにする。(新字源)
10.合従連衡(がっしょうれんこう):その時の利害に従って、結びついたり離れたりすること。また,時勢に応じて巧みに計略をめぐらす政策、とくに外交政策をいう。合従=縦に合わせる意で、南北の同盟をいう。連衡=横に連なる意で、東西に連合すること。(新明解故事ことわざ辞典)
11.乾坤一擲(けんこんいってき):運を天にまかせ,のるかそるかの大勝負をすること。天下をかけて一回さいころを投げる意から。乾坤=「乾」は天、「坤」は地の意(新明解故事ことわざ辞典)→類を以て集まるを見てください。
12.面目躍如(めんもくやくじょ):「面目」③体面,世間の人に対する顔「躍如」①おどりあがるさま。(新字源)
要領を得ず(ようりょうをえず):物事のいちばん大切なところをつかんでいないたとえ。また,何が何だかよくわからないこと。出典史記(新明解故事ことわざ辞典)
国会で漢字検定が行われた。読みの問題である。(出題・解答は文末参照)しかし重要なのは意味で考えるべきなので出題文『強い日本を!私の国家再建計画』(文藝春秋2008年11月号)を読んでみた。引用文は長文で修飾語が多いため論理を整理して読み下した後,解釈を試みる。
『総裁選における7割の得票は望外であり,就中,地方での圧勝は私の宝だと思ったが所詮準決勝でしかない。』
>宝が所詮○○なしとはえらく軽いものだったらしい。そのわりにまだ決勝戦は始まっていない。
『決勝戦たる総選挙で我々が勝たなければならい。危機(=衆参のねじれ)から逃げ、あるいは唯々諾々と政権を手放せば、国の舵取りを過つことになる。』
>ねじれは国民の選択の結果であり,逃れることはできないし,逆らうこともできない。
『Japain【日本の苦悩(失われた10年)】と揶揄される日本の存在感の低下は国家に対する国民の信頼感を痛めた。』
>政治が苦悩を生み,信頼感を低下させたのである。存在感の低下が信頼感を痛めるというのは論理的でない。
『もう一度国民の審判を仰ぎたい。日本経済を再生し改革を続行する見取り図と手だてを提起するのは畢竟、そのためである。』
>国民の審判を受けるためか,日本経済を再生するためか,改革を続行するためか畢竟,目的はなんだろう。
『国民の真剣なまなざしは,衆参ねじれの危機を解決して強い政治に立ち戻れ,と希求する叱咤激励の視線だと私は思った。』>まなざしは視線に違いないが,大声は出せない。希求するのは弱い立場の者,激励するのは同位か強い立場の者である。国民の視点をどの位置に置いているのかわからない。
全部で12あるようだが,疲れたので明日に続ける。昨日は17条の憲法で涙が出てきたが,今日は欠伸しか出ない。
1.就中(なかんずく):(ナカニツクの音便)その中で。とりわけて。特に。(広辞苑)
2.唯々諾々(いいだくだく):事のよしあしにかかわらず人のことばに従うこと。「唯」は「はい」とつつしんですぐに答えることば。「諾」は「はい」とゆっくり答える。(新字源)
3.揶揄(やゆ):手をあげてからかう。あざける。「揶」からかう。あざける。「揄」①ひく②ほめそやす③からかう。なぶる。(新字源)
4.畢竟(ひっきょう):終局の意。つまり。結局。「畢」①あみ②かり③星座の名④おわる⑤つくす⑥ついに⑦ことごとく「竟」①つきる②おわる③きわめる④わたる⑤ついに。(新字源)
5.叱咤激励(しったげきれい):「叱咤」大声でしかりつける。大声でどなる。(史記淮陰侯伝)「激励」はげます。つとめはげむ。(新字源)
6.中興の祖(ちゅうこうのそ):「中興」おとろえていたのがふたたびさかんになること。「祖」④物事のもとを開いた者。(新字源)
7.窶し(やつし):「窶」まずしい。やつれる。やせおとろえる。(新字源)
8.朝令暮改(ちょうれいぼかい):→朝令暮改を見てください。
9.愚弄(ぐろう):人をばかにする。あなどってなぶりものにする。「愚」①おろか④あなどる「弄」①もてあそぶ,ほしいままにする。(新字源)
10.合従連衡(がっしょうれんこう):その時の利害に従って、結びついたり離れたりすること。また,時勢に応じて巧みに計略をめぐらす政策、とくに外交政策をいう。合従=縦に合わせる意で、南北の同盟をいう。連衡=横に連なる意で、東西に連合すること。(新明解故事ことわざ辞典)
11.乾坤一擲(けんこんいってき):運を天にまかせ,のるかそるかの大勝負をすること。天下をかけて一回さいころを投げる意から。乾坤=「乾」は天、「坤」は地の意(新明解故事ことわざ辞典)→類を以て集まるを見てください。
12.面目躍如(めんもくやくじょ):「面目」③体面,世間の人に対する顔「躍如」①おどりあがるさま。(新字源)