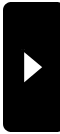2009年01月21日
(か)株を守りて兎を待つ,夏炉冬扇
「緊急経済対策の内容は株を守りて兎を待つに等しいし,これだけ遅れたら夏炉冬扇じゃないか?」と使う。
株を守りて兎を待つ(かぶをまもりてうさぎをまつ):古い習慣にこだわり,進歩がないことのたとえ。また,偶然に成功した経験に味をしめて,もう一度同じ方法によって成功しようとすることのたとえ。出典韓非子(新明解故事ことわざ辞典)
夏炉冬扇(かろとうせん):時期はずれで役に立たない物のたとえ。また,無益で役に立たない才能や言論のたとえ。夏のいろりや,冬の扇子の意から。出典論衡(新明解故事ことわざ辞典)
どれほどすごい緊急経済対策かと思って,内閣府の資料で調てみた。知らしむべからず依らしむべしなのか非常にわかりにくい資料だった。それによれば,平成10年の緊急経済対策と比べて規模は23兆円が75兆円(どう足し算しても62兆円にしかならなかったが)に増えているものの,内容に変化のないものだった。確かに省エネ・介護・子育てなどで1.3兆円ほどあるが,その中には消費者庁の設置や消えた年金の対策費も入っている。金額の大きいものでは金融・貸し渋り対策5.9兆円(H10)が52兆円になっているが,放漫経営や変化に対応できない企業救済を含んだ信用保証,銀行の不良債権買い取りのようなもので,効果のほどは疑わしい。増加分はほとんどこれである。逆に平成10年には減税(所得・事業)と地域振興券で10兆円あったものが,今回は減税と定額給付金合計で2.3兆円に下がっている。減税と給付金はGDPにとっての効果は同じであり,それが極端に下がっている。なにをもって経済通が作った予算というのだろうか?国会は末節にこだわって根本の議論を忘れている。
【因釋其耒而守株,冀復得兔,兔不可復得,而身為宋國笑。】韓非子五蠹
【作無益之能納無補之説以夏進炉以冬奏扇】論衡逢遇
余談
論衡には「周の成王の時(紀元前1020年頃),倭人が鬯草(祭酒の原料である香料の一種)を貢献した」との記述があり,事実であれば,日本人が歴史に初めて登場した記録である(文献1)。その800年後,秦の始皇帝が不老長寿の薬草を求めて徐福を東海に派遣した(紀元前210年頃)ときの終焉地は日本であるとの伝承がある。魏志倭人伝に卑弥呼が登場するのは450年後の239年,遣隋使はさらに下って607年である。徐福の向かった先は「蓬萊」、「方丈」、「瀛州」の三神山であったが,そういえば滋賀県には蓬萊山があって歴史の興味はつきない。
参考文献1:「日本漢學史」 牧野謙次郎 述/三浦叶 筆記,[日]世界堂書店,1938
株を守りて兎を待つ(かぶをまもりてうさぎをまつ):古い習慣にこだわり,進歩がないことのたとえ。また,偶然に成功した経験に味をしめて,もう一度同じ方法によって成功しようとすることのたとえ。出典韓非子(新明解故事ことわざ辞典)
夏炉冬扇(かろとうせん):時期はずれで役に立たない物のたとえ。また,無益で役に立たない才能や言論のたとえ。夏のいろりや,冬の扇子の意から。出典論衡(新明解故事ことわざ辞典)
どれほどすごい緊急経済対策かと思って,内閣府の資料で調てみた。知らしむべからず依らしむべしなのか非常にわかりにくい資料だった。それによれば,平成10年の緊急経済対策と比べて規模は23兆円が75兆円(どう足し算しても62兆円にしかならなかったが)に増えているものの,内容に変化のないものだった。確かに省エネ・介護・子育てなどで1.3兆円ほどあるが,その中には消費者庁の設置や消えた年金の対策費も入っている。金額の大きいものでは金融・貸し渋り対策5.9兆円(H10)が52兆円になっているが,放漫経営や変化に対応できない企業救済を含んだ信用保証,銀行の不良債権買い取りのようなもので,効果のほどは疑わしい。増加分はほとんどこれである。逆に平成10年には減税(所得・事業)と地域振興券で10兆円あったものが,今回は減税と定額給付金合計で2.3兆円に下がっている。減税と給付金はGDPにとっての効果は同じであり,それが極端に下がっている。なにをもって経済通が作った予算というのだろうか?国会は末節にこだわって根本の議論を忘れている。
【因釋其耒而守株,冀復得兔,兔不可復得,而身為宋國笑。】韓非子五蠹
【作無益之能納無補之説以夏進炉以冬奏扇】論衡逢遇
余談
論衡には「周の成王の時(紀元前1020年頃),倭人が鬯草(祭酒の原料である香料の一種)を貢献した」との記述があり,事実であれば,日本人が歴史に初めて登場した記録である(文献1)。その800年後,秦の始皇帝が不老長寿の薬草を求めて徐福を東海に派遣した(紀元前210年頃)ときの終焉地は日本であるとの伝承がある。魏志倭人伝に卑弥呼が登場するのは450年後の239年,遣隋使はさらに下って607年である。徐福の向かった先は「蓬萊」、「方丈」、「瀛州」の三神山であったが,そういえば滋賀県には蓬萊山があって歴史の興味はつきない。
参考文献1:「日本漢學史」 牧野謙次郎 述/三浦叶 筆記,[日]世界堂書店,1938
2009年01月20日
(わ)和を以て貴しと為す
「和を以て貴しと為すというが,礼節も規律もなければ単なる烏合(うごう)の衆でしかない」と使う。
和を以て貴しと為す(わをもってとうとしとなす):人々がお互いに仲良くやっていくことがもっとも大切なことである。何事も調和が大事であるということ。聖徳太子の定めた十七条憲法の第一条に出てくることば。また「礼記」には「礼は之(これ)和を用(も)って貴しと為す」とある。(新明解故事ことわざ辞典)
曽我・物部の内戦と曽我馬子による祟峻天皇の暗殺の後,摂政となった聖徳太子は冠位十二階,十七条憲法を定め国家体制を整え,遣隋使の派遣など平和・独立・対等の外交を展開した。十七条憲法は「統一され秩序正しく効率的で有徳な,そして,対外的に独立した新平和国家の創造のためのマニフェスト」(参考文献1)である。
よくできたマニフェストなので要点を抜き出して,解釈してみる。
(おもに政治を司る者に向けての条文である)
1条.「和」が最上の価値であり,従順になれ。議論すれば道理がはっきりし,良い結果を生む。
2条.仏・法・僧を大切にせよ。生き物を大切にするというのは世界中が認める教えである。
3条.君命は天の言葉であり,謹んで聞け。逆らえば天地がひっくりかえるような大事になる。
4条.政治を行う者は礼をわきまえよ。政治を行う者に礼が無いと民の礼は乱れて犯罪が増える。
5条.贅沢や欲望をなくして民の声によく耳を傾けよ。貧しい民の声はなかなか届いてこない。
6条.善い者は顕彰し,悪い者には懲罰を与えよ。上にへつらい下を扇動する者は国乱の元である。
7条.職責を全うし,職権を濫用するな。職務に人が要るのであって,人のための職務ではない。
8条.朝早く出仕し,遅くまで働け。さもないと緊急事態に対応できず,仕事が後回しになる。
9条.うそを言わず正しいことを行え。善いことと悪いことに分けないと何事も進まない。
10条.感情は殺せ。人によって考えが違う。人が怒っていたら自分が間違っていないかまず考えよ。
11条.上官は下官の仕事ぶりをよく見よ。功績には賞を与え過失には罰を与えよ。
12条.勝手に税を徴収するな。国家のために民の税があり,個々の役職のためにあるのではない。
13条.後任者は前任者に勝る職務を行え。聞いていないなどと前任者の責任にしてはならない。
14条.嫉妬するな。国家を治めることのできる千年に一人の優れた人材が出て来れない。
15条.公私混同するな。私怨によって不和が起き公務が疎かになる。1条を読め。
16条.民を使うときは時機を考えよ。衣食を蓄えるべき時期に労役を科すとどうなるか理解せよ。
17条.独断するな。重要な事ほどささいな間違いが大きく影響する。皆でよく議論せよ。
儒教・仏教・道教多彩であるが,訳している途中で不覚にも涙が出てきて止まらなくなった。
1400年経っても状況は変わらない。人材は現れていないのだ。
現在でもこのマニフェストは通用する。有れば必ず一票を投じたくなる。
誤解を恐れず,関連する故事成語を書いておく。
1条「礼は之に和を用(もっ)て貴しとなす」礼記
4条「礼は未然の前に禁じ,法は已然の後に施す」史記
6条「勧善懲悪」春秋左氏伝
8条「朝に其の事を忘るれば,夕に其の功を失う」管子
10条「怒りには則ち理を思い,危うきには義を忘れず」説苑
11条「信賞必罰」韓非子
参考文献1
深瀬忠一「聖徳太子の17条の憲法(とくに「以和為貴」)にたいする中国諸思想の影響と日本的総合およびその憲法文化的遺産と今日的意義(1)」,北星論集(経)第32号,1995
和を以て貴しと為す(わをもってとうとしとなす):人々がお互いに仲良くやっていくことがもっとも大切なことである。何事も調和が大事であるということ。聖徳太子の定めた十七条憲法の第一条に出てくることば。また「礼記」には「礼は之(これ)和を用(も)って貴しと為す」とある。(新明解故事ことわざ辞典)
曽我・物部の内戦と曽我馬子による祟峻天皇の暗殺の後,摂政となった聖徳太子は冠位十二階,十七条憲法を定め国家体制を整え,遣隋使の派遣など平和・独立・対等の外交を展開した。十七条憲法は「統一され秩序正しく効率的で有徳な,そして,対外的に独立した新平和国家の創造のためのマニフェスト」(参考文献1)である。
よくできたマニフェストなので要点を抜き出して,解釈してみる。
(おもに政治を司る者に向けての条文である)
1条.「和」が最上の価値であり,従順になれ。議論すれば道理がはっきりし,良い結果を生む。
2条.仏・法・僧を大切にせよ。生き物を大切にするというのは世界中が認める教えである。
3条.君命は天の言葉であり,謹んで聞け。逆らえば天地がひっくりかえるような大事になる。
4条.政治を行う者は礼をわきまえよ。政治を行う者に礼が無いと民の礼は乱れて犯罪が増える。
5条.贅沢や欲望をなくして民の声によく耳を傾けよ。貧しい民の声はなかなか届いてこない。
6条.善い者は顕彰し,悪い者には懲罰を与えよ。上にへつらい下を扇動する者は国乱の元である。
7条.職責を全うし,職権を濫用するな。職務に人が要るのであって,人のための職務ではない。
8条.朝早く出仕し,遅くまで働け。さもないと緊急事態に対応できず,仕事が後回しになる。
9条.うそを言わず正しいことを行え。善いことと悪いことに分けないと何事も進まない。
10条.感情は殺せ。人によって考えが違う。人が怒っていたら自分が間違っていないかまず考えよ。
11条.上官は下官の仕事ぶりをよく見よ。功績には賞を与え過失には罰を与えよ。
12条.勝手に税を徴収するな。国家のために民の税があり,個々の役職のためにあるのではない。
13条.後任者は前任者に勝る職務を行え。聞いていないなどと前任者の責任にしてはならない。
14条.嫉妬するな。国家を治めることのできる千年に一人の優れた人材が出て来れない。
15条.公私混同するな。私怨によって不和が起き公務が疎かになる。1条を読め。
16条.民を使うときは時機を考えよ。衣食を蓄えるべき時期に労役を科すとどうなるか理解せよ。
17条.独断するな。重要な事ほどささいな間違いが大きく影響する。皆でよく議論せよ。
儒教・仏教・道教多彩であるが,訳している途中で不覚にも涙が出てきて止まらなくなった。
1400年経っても状況は変わらない。人材は現れていないのだ。
現在でもこのマニフェストは通用する。有れば必ず一票を投じたくなる。
誤解を恐れず,関連する故事成語を書いておく。
1条「礼は之に和を用(もっ)て貴しとなす」礼記
4条「礼は未然の前に禁じ,法は已然の後に施す」史記
6条「勧善懲悪」春秋左氏伝
8条「朝に其の事を忘るれば,夕に其の功を失う」管子
10条「怒りには則ち理を思い,危うきには義を忘れず」説苑
11条「信賞必罰」韓非子
参考文献1
深瀬忠一「聖徳太子の17条の憲法(とくに「以和為貴」)にたいする中国諸思想の影響と日本的総合およびその憲法文化的遺産と今日的意義(1)」,北星論集(経)第32号,1995
2009年01月19日
(を)温故知新
「鉱山時代の精錬の技術が,廃棄物から金を取り出すのに使えるなんてまさに温故知新だね」と使う。
温故知新(おんこちしん):故(ふる)きを温(たず)ねて新しきを知る。前に学んだことや昔の事柄をよく調べ研究して,そこから新しい知識や道理を発見すること。孔子が先生の資格として述べたことば。温(たず)ねては温(あたた)めてとも読む。(新明解故事ことわざ辞典)
温(あたた)めることが,温(たず)ねることなのか?
諸子百家の書籍に出てくる「温」の字とたずねる意味の「尋」「訊」「訪」の字の出現数を調べてみた。(下図)
「故きをたずねる」意味として使われた例は論語と禮記(どちらも孔子の言葉として)の2例以外に見当たらない。それ以外の「温」はすべて気候や温度の意味あるいは,温和など人の形容として使われている。たずねる意の3文字もそれぞれ使用されており,「温」が「たずねる」意味とする根拠は見つからなかった。

次に,「温故」は上の2例以降にどのように使われているかを調べた。(下図)

ほとんどが「溫故知新」の一語として使われており,「溫故而知新」がその語源であることを示している。つまり,この時点で意味だけが必要で,「あたためる」か「たずねる」かにこだわる必要はなくなっている。
つまり,温を「たずねる」とする根拠はなく,「あたためる」に読みを統一するべきである。
冒頭の例文は,銅鉱山及び精錬が斜陽産業となった折,雇用確保を最優先として得意技術の転用をすすめ,今では携帯電話や家電製品など廃棄物から貴金属を抽出する事業を成功させた企業への讃辞である。安易に人減らしを行う企業に人は育たず,固有技術の蓄積はないと銘すべきである。リーダーとなるには何より「あたたかみ」が必要なのである。
【子曰:“溫故而知新,可以為師矣。”】論語為政
温故知新(おんこちしん):故(ふる)きを温(たず)ねて新しきを知る。前に学んだことや昔の事柄をよく調べ研究して,そこから新しい知識や道理を発見すること。孔子が先生の資格として述べたことば。温(たず)ねては温(あたた)めてとも読む。(新明解故事ことわざ辞典)
温(あたた)めることが,温(たず)ねることなのか?
諸子百家の書籍に出てくる「温」の字とたずねる意味の「尋」「訊」「訪」の字の出現数を調べてみた。(下図)
「故きをたずねる」意味として使われた例は論語と禮記(どちらも孔子の言葉として)の2例以外に見当たらない。それ以外の「温」はすべて気候や温度の意味あるいは,温和など人の形容として使われている。たずねる意の3文字もそれぞれ使用されており,「温」が「たずねる」意味とする根拠は見つからなかった。

次に,「温故」は上の2例以降にどのように使われているかを調べた。(下図)

ほとんどが「溫故知新」の一語として使われており,「溫故而知新」がその語源であることを示している。つまり,この時点で意味だけが必要で,「あたためる」か「たずねる」かにこだわる必要はなくなっている。
つまり,温を「たずねる」とする根拠はなく,「あたためる」に読みを統一するべきである。
冒頭の例文は,銅鉱山及び精錬が斜陽産業となった折,雇用確保を最優先として得意技術の転用をすすめ,今では携帯電話や家電製品など廃棄物から貴金属を抽出する事業を成功させた企業への讃辞である。安易に人減らしを行う企業に人は育たず,固有技術の蓄積はないと銘すべきである。リーダーとなるには何より「あたたかみ」が必要なのである。
【子曰:“溫故而知新,可以為師矣。”】論語為政
2009年01月18日
(る)類を以て集まる
「あの3人組を見てみろよ。『類を以て集まる』というか髪型も持ち物も歩き方まで一緒だぜ」と使う。
類を以て集まる(るいをもってあつまる):似た者同士は自然に寄り集まるということ。また,善人のまわりには善人が集まり,悪人は悪人同士で仲間になるということ。いろはかるた(京都)の一。(新明解故事ことわざ辞典)
日常生活で感じる「似た者同士は自然に寄り集まる」感は否めない。
しかし,いったい何が似ているのか?なぜ似ていると集まるのか?集ったから似てしまったのではないのだろうか?などの疑問は湧く。
人口に膾炙(かいしゃ)している割には,論理の不明確な成語である。原文で確かめてみよう。
原文は【方以類聚,物以羣分,吉凶生矣。】周易繫辭上
方は類を以て聚(あつま)り,物は群を以て分かれ,吉凶を生ず。と読める。
では方とは何か?前文を読んでみよう。
前文は易の言辞に関する補足の形で書かれた文であるので易の考え方を押さえながら解釈してみたい。解釈には明治書院新釈漢文大系易経下を参考にした。
『(天は高くして上にあって万物を覆い,地は低くして下にあって万物を載せている。)天は高い(これを陽)とし,地は低い(これを陰)とすれば(陰陽説に従ってもっとも陽である)乾と(もっとも陰である)坤が定まる。(天と地の間にあるもの,すなわち万物は)低い場所から高い場所まで秩序をもって列なっており,その位置によって貴賤が定められる。(天と地の間で起こるできごと,すなわち万象には陽である)動(うごくものと陰である)静(うごかないもの)が常にあり,(万物は陽である)剛(かたいものと陰である)柔(やわらかいもの)に分かれている。(万象は善に向く場合と悪に向く場合があり)その方向を種類によって集め,(万物は善である)物(と悪である物)の群に分けて,(この組み合わせによって)吉凶が生まれる。』
つまり,方とは善悪の分類の仕方で,同じような事象を集めたものということになる。
論理は明確になった。
疑問の答えは,
Q1いったい何が似ているのか? A1(善悪の向かう)方向が似ています。
Q2なぜ似ていると集まるのか? A2そうは言っていません。(向かう方向が同じだと)同じに類に見なしているだけです。
Q3集ったから似てしまったのではないのだろうか? A3いいえ,方向が同じだけで,同じ場所かどうかは問題にしていません。
となる。
まったく質問の答えになっていない。
もしかすると,命題の「類を以て集まる」は偽であって「(方は)類を以て集める」が真ではないか。私には易の理解は当分できそうにない。
ただし,陽と陰(あるいは善と悪)など森羅万象を簡単に区別できるフレームワークを考えることは有意義である。
さて,政府与党と野党は乾坤一擲,雌雄を決する,白黒をつける,一か八か,伸(の)るか反(そ)るかの大勝負だと言っている。(陰陽説に基づく対決の構造は案外多い)
だが,両者が向かう方向の違いはよく見えない。未だ類を以て集まる域を脱していないのだ。
原文:【天尊地卑,乾坤定矣。卑高以陳,貴賤位矣。動靜有常,剛柔斷矣。方以類聚,物以羣分,吉凶生矣。】
類を以て集まる(るいをもってあつまる):似た者同士は自然に寄り集まるということ。また,善人のまわりには善人が集まり,悪人は悪人同士で仲間になるということ。いろはかるた(京都)の一。(新明解故事ことわざ辞典)
日常生活で感じる「似た者同士は自然に寄り集まる」感は否めない。
しかし,いったい何が似ているのか?なぜ似ていると集まるのか?集ったから似てしまったのではないのだろうか?などの疑問は湧く。
人口に膾炙(かいしゃ)している割には,論理の不明確な成語である。原文で確かめてみよう。
原文は【方以類聚,物以羣分,吉凶生矣。】周易繫辭上
方は類を以て聚(あつま)り,物は群を以て分かれ,吉凶を生ず。と読める。
では方とは何か?前文を読んでみよう。
前文は易の言辞に関する補足の形で書かれた文であるので易の考え方を押さえながら解釈してみたい。解釈には明治書院新釈漢文大系易経下を参考にした。
『(天は高くして上にあって万物を覆い,地は低くして下にあって万物を載せている。)天は高い(これを陽)とし,地は低い(これを陰)とすれば(陰陽説に従ってもっとも陽である)乾と(もっとも陰である)坤が定まる。(天と地の間にあるもの,すなわち万物は)低い場所から高い場所まで秩序をもって列なっており,その位置によって貴賤が定められる。(天と地の間で起こるできごと,すなわち万象には陽である)動(うごくものと陰である)静(うごかないもの)が常にあり,(万物は陽である)剛(かたいものと陰である)柔(やわらかいもの)に分かれている。(万象は善に向く場合と悪に向く場合があり)その方向を種類によって集め,(万物は善である)物(と悪である物)の群に分けて,(この組み合わせによって)吉凶が生まれる。』
つまり,方とは善悪の分類の仕方で,同じような事象を集めたものということになる。
論理は明確になった。
疑問の答えは,
Q1いったい何が似ているのか? A1(善悪の向かう)方向が似ています。
Q2なぜ似ていると集まるのか? A2そうは言っていません。(向かう方向が同じだと)同じに類に見なしているだけです。
Q3集ったから似てしまったのではないのだろうか? A3いいえ,方向が同じだけで,同じ場所かどうかは問題にしていません。
となる。
まったく質問の答えになっていない。
もしかすると,命題の「類を以て集まる」は偽であって「(方は)類を以て集める」が真ではないか。私には易の理解は当分できそうにない。
ただし,陽と陰(あるいは善と悪)など森羅万象を簡単に区別できるフレームワークを考えることは有意義である。
さて,政府与党と野党は乾坤一擲,雌雄を決する,白黒をつける,一か八か,伸(の)るか反(そ)るかの大勝負だと言っている。(陰陽説に基づく対決の構造は案外多い)
だが,両者が向かう方向の違いはよく見えない。未だ類を以て集まる域を脱していないのだ。
原文:【天尊地卑,乾坤定矣。卑高以陳,貴賤位矣。動靜有常,剛柔斷矣。方以類聚,物以羣分,吉凶生矣。】
2009年01月17日
(ぬ)濡れ衣
「裁判員と言っても法律にはずぶの素人だから,濡れ衣を着せられる人が増えるだろう。」
あるいは
「将軍は『やむを得ない戦争であって,侵略だと批難されるのは濡れ衣だ』と主張している。」
などと使う。
濡衣を着る(ぬれぎぬをきる):無実の罪を受けること。また,根も葉もない悪いうわさをたてられること。(新明解故事ことわざ辞典)
濡れ衣の語源は,諸説ある。
①濡衣塚伝説など,濡れた衣が犯罪の証拠としてねつ造された。
②犯罪の結果,濡れてしまった衣を他人に着せて責任を転嫁した。
③衣が乾けば無罪,濡れたままなら有罪とみなした神明裁判が行われた。
(②③は出典不明)などである。すべて冤罪となる可能性がある。
しかし,(科学的かどうかは別にして)その時代の法を正とした裁判は行われたであろう。
上の2例はどの説に当たるのか?
ところで,法の変更が多くの人民に濡れ衣を着せることになった例がある。
...(王宮が火災になったとき下された命令はこのようなものだ)「火事から人を助けて死んだ者は,戦死した者と同じ賞とする。火事から人を助けても死ななかった者は,戦勝した者と同じ賞とする。火事で人を助けなかった者は敵前逃亡した者と同じ罪とする。」すると人々は皆泥を顔に塗り,濡衣を被って火に走っていく者が左から3000人,右から3000人...(韓非子內儲說上)
濡れ衣の原因は存外,証拠や裁判のやり方ではなく,法そのものにあるのかも知れぬ。
【“人之救火者死,比死敵之賞。救火而不死者,比勝敵之賞。不救火者,比降北之罪。”人塗其體、被濡衣而走火者,左三千人,右三千人。】韓非子內儲說上
余談
濡れ衣の語源として「実の無い(無実)から蓑(みの)ないに転じ,濡れ衣に通じる」というのもある。(出典不明)
あるいは
「将軍は『やむを得ない戦争であって,侵略だと批難されるのは濡れ衣だ』と主張している。」
などと使う。
濡衣を着る(ぬれぎぬをきる):無実の罪を受けること。また,根も葉もない悪いうわさをたてられること。(新明解故事ことわざ辞典)
濡れ衣の語源は,諸説ある。
①濡衣塚伝説など,濡れた衣が犯罪の証拠としてねつ造された。
②犯罪の結果,濡れてしまった衣を他人に着せて責任を転嫁した。
③衣が乾けば無罪,濡れたままなら有罪とみなした神明裁判が行われた。
(②③は出典不明)などである。すべて冤罪となる可能性がある。
しかし,(科学的かどうかは別にして)その時代の法を正とした裁判は行われたであろう。
上の2例はどの説に当たるのか?
ところで,法の変更が多くの人民に濡れ衣を着せることになった例がある。
...(王宮が火災になったとき下された命令はこのようなものだ)「火事から人を助けて死んだ者は,戦死した者と同じ賞とする。火事から人を助けても死ななかった者は,戦勝した者と同じ賞とする。火事で人を助けなかった者は敵前逃亡した者と同じ罪とする。」すると人々は皆泥を顔に塗り,濡衣を被って火に走っていく者が左から3000人,右から3000人...(韓非子內儲說上)
濡れ衣の原因は存外,証拠や裁判のやり方ではなく,法そのものにあるのかも知れぬ。
【“人之救火者死,比死敵之賞。救火而不死者,比勝敵之賞。不救火者,比降北之罪。”人塗其體、被濡衣而走火者,左三千人,右三千人。】韓非子內儲說上
余談
濡れ衣の語源として「実の無い(無実)から蓑(みの)ないに転じ,濡れ衣に通じる」というのもある。(出典不明)