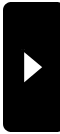2009年01月11日
(に)似て非なる者を悪(にく)む
【孔子曰,惡似而非者。惡莠,恐其亂苗也。惡佞,恐其亂義也。...】出典:孟子(盡心下)
孔子曰く,似て非なる者を惡む。莠(いう)を惡むは,其の苗(なへ)を亂(みだ)るを恐るればなり。
佞(ねい)を惡むは,其の義を亂るを恐るればなり。...
孔子は言っている,『自分は似て非なるものを悪む。たとえば莠を悪むのは,それが(穀物の)苗ににてまぎらわしいことを恐れるからである。佞弁を悪むのは,その言にあたかも義があるように聞こえるため,そのまぎらわしいことを恐れるからである。
(参考:新釈漢文大系第4巻孟子,明治書院)
莠:えのころぐさ,ねこじゃらし(広辞苑)
佞:口先が巧みで心の正しからぬこと(広辞苑)
義:人間の行うべきすじみち(広辞苑)
続けて似て非なるものの例として 『利口(多弁で誠実のないこと)と信,鄭聲(鄭の淫靡な音楽)と樂(正しい音楽),紫(色)と朱(色),鄉原(一郷の人々がいい人だという偽善の人)と德』 を挙げている。
--------------------------------------------------------------------------------------------------
さて,2300年後の日本郷は,国力の低下,景気の低迷,食糧自給率の低下,少子高齢化,格差拡大など亡国の様相である。
雇用,年金,医療・介護,食の安全など民の生存に直接かかわる危機ばかりである。
佞臣,義臣入り乱れての緊急なる百策が繚乱して,どれが莠で苗かもわからぬ。
毒まんじゅうもあるらしい。急ぎ似て非なるものを自ら見極めねばならぬ。
亡国の民の話題は,雇い止め,ワークシェアリング,出産・育児と仕事の両立,消えた・消された年金,年金支給年齢の引き上げ,医師不足,医療・介護保険料増,産地偽装,汚染米,切りがない。
しかし,これらはすべて民の勤労と勤労の対価に関わる問題である。そしてそれらの使い方(消費と税)の問題なのである。
これは似ずとも非ならざぬ疑いのない国策の問題なのである。
余談
『覇王』で,覇は国の大きさと行いのすさまじさでどこにでも見つかるが,王は見つからないことを書いた。『似て非なるもの』の例示も同様で,どうも孟子という人は測れるものと測れないものを一緒に論じるようである。
孔子曰く,似て非なる者を惡む。莠(いう)を惡むは,其の苗(なへ)を亂(みだ)るを恐るればなり。
佞(ねい)を惡むは,其の義を亂るを恐るればなり。...
孔子は言っている,『自分は似て非なるものを悪む。たとえば莠を悪むのは,それが(穀物の)苗ににてまぎらわしいことを恐れるからである。佞弁を悪むのは,その言にあたかも義があるように聞こえるため,そのまぎらわしいことを恐れるからである。
(参考:新釈漢文大系第4巻孟子,明治書院)
莠:えのころぐさ,ねこじゃらし(広辞苑)
佞:口先が巧みで心の正しからぬこと(広辞苑)
義:人間の行うべきすじみち(広辞苑)
続けて似て非なるものの例として 『利口(多弁で誠実のないこと)と信,鄭聲(鄭の淫靡な音楽)と樂(正しい音楽),紫(色)と朱(色),鄉原(一郷の人々がいい人だという偽善の人)と德』 を挙げている。
--------------------------------------------------------------------------------------------------
さて,2300年後の日本郷は,国力の低下,景気の低迷,食糧自給率の低下,少子高齢化,格差拡大など亡国の様相である。
雇用,年金,医療・介護,食の安全など民の生存に直接かかわる危機ばかりである。
佞臣,義臣入り乱れての緊急なる百策が繚乱して,どれが莠で苗かもわからぬ。
毒まんじゅうもあるらしい。急ぎ似て非なるものを自ら見極めねばならぬ。
亡国の民の話題は,雇い止め,ワークシェアリング,出産・育児と仕事の両立,消えた・消された年金,年金支給年齢の引き上げ,医師不足,医療・介護保険料増,産地偽装,汚染米,切りがない。
しかし,これらはすべて民の勤労と勤労の対価に関わる問題である。そしてそれらの使い方(消費と税)の問題なのである。
これは似ずとも非ならざぬ疑いのない国策の問題なのである。
余談
『覇王』で,覇は国の大きさと行いのすさまじさでどこにでも見つかるが,王は見つからないことを書いた。『似て非なるもの』の例示も同様で,どうも孟子という人は測れるものと測れないものを一緒に論じるようである。
2009年01月10日
(は)覇王
【以力假仁者霸,霸必有大國。以德行仁者王,王不待大。】出典:孟子(公孫丑上)
力を以て仁(じん)を假(か)る者は覇たり,覇は必ず大國を有(たも)つ。
徳を以て仁を行う者は王たり,王は大を待たず。
(本当は)力ずくだが,仁に見せかける者は覇である。だから覇者は必ず(実行力の伴う)大国である。
徳を以て仁を行う者は王である。王者は大(国)である必要はない。
(参考:新釈漢文大系第4巻孟子,明治書院)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
ここで徳とは,仁・義・礼・智であり,仁とはいつくしみ,慈愛,博愛などの心ということにしておく。
覇者と王者,覇道と王道,同じようなものだと思っていたが別モノらしい。
では, 『見せかけの仁』 と 『本物の仁』 はどうやって見分けるのだろうか?
私には無理だと思う。
なぜなら,仁は国や文化や宗教やひとりひとりで異なる筈だと思うからである。
さて,孟子の時代から2300年間,洋の東西を問わずあまたの国が覇を唱え,必ず失墜している。
大国を計る尺度も軍事・経済・資源とさまざまに変わったが,王を唱えた国はまだない。
力を以て仁(じん)を假(か)る者は覇たり,覇は必ず大國を有(たも)つ。
徳を以て仁を行う者は王たり,王は大を待たず。
(本当は)力ずくだが,仁に見せかける者は覇である。だから覇者は必ず(実行力の伴う)大国である。
徳を以て仁を行う者は王である。王者は大(国)である必要はない。
(参考:新釈漢文大系第4巻孟子,明治書院)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
ここで徳とは,仁・義・礼・智であり,仁とはいつくしみ,慈愛,博愛などの心ということにしておく。
覇者と王者,覇道と王道,同じようなものだと思っていたが別モノらしい。
では, 『見せかけの仁』 と 『本物の仁』 はどうやって見分けるのだろうか?
私には無理だと思う。
なぜなら,仁は国や文化や宗教やひとりひとりで異なる筈だと思うからである。
さて,孟子の時代から2300年間,洋の東西を問わずあまたの国が覇を唱え,必ず失墜している。
大国を計る尺度も軍事・経済・資源とさまざまに変わったが,王を唱えた国はまだない。
2009年01月09日
(ろ)壟断(ろうだん)
【有賤丈夫焉,必求龍斷而登之,以左右望而罔市利。】出典:孟子(公孫丑下)
『賤丈夫有り、必ず壟断を求めて登り、左右を望みて市利を罔せり。』 と読み,意味は 『いやしい男が高い所から市場を見下ろして商売に都合のよい場所を見定め、利益を独占した(Yahoo辞書大辞泉)』 である。
ところで,壟断とは 『岡の断ち切ったようにそびえたところ(広辞苑第二版)』 らしいが,いくら金儲けとはいえそんな危険なところを登るのか?と疑問に思い調べてみた。
壟は 『①うね..②つか..(新字源二八一版)』 で人工のこんもりした盛り土のことのようだ。そびえるには低すぎる高さである。
それに断崖や断層など 『断某』 であれば(高さの疑問をを除けば)切り立った感はあるが,これは 『某断』 なのである。裁断・判断・決断など 『某断』 は何かをさばいている感じである。
つまり 『こんもりとした盛り土の上に陣取り,何かをさばくこと』 としたほうがすんなりイメージがわく。そこで自分に都合のよい裁定を行って 『利益を独占する』 という意味がぴたりとはまる。
孟子は魯の宰相の世襲を 『壟断』 であると批判してこの例え話を持ち出した。お山の大将が利権を独占しそれを身内に引き継いでいく図は今も変わらない。世襲然り,天下り然りである。ただしその山は性善説を以てする孟子には必ず低いのである。
『賤丈夫有り、必ず壟断を求めて登り、左右を望みて市利を罔せり。』 と読み,意味は 『いやしい男が高い所から市場を見下ろして商売に都合のよい場所を見定め、利益を独占した(Yahoo辞書大辞泉)』 である。
ところで,壟断とは 『岡の断ち切ったようにそびえたところ(広辞苑第二版)』 らしいが,いくら金儲けとはいえそんな危険なところを登るのか?と疑問に思い調べてみた。
壟は 『①うね..②つか..(新字源二八一版)』 で人工のこんもりした盛り土のことのようだ。そびえるには低すぎる高さである。
それに断崖や断層など 『断某』 であれば(高さの疑問をを除けば)切り立った感はあるが,これは 『某断』 なのである。裁断・判断・決断など 『某断』 は何かをさばいている感じである。
つまり 『こんもりとした盛り土の上に陣取り,何かをさばくこと』 としたほうがすんなりイメージがわく。そこで自分に都合のよい裁定を行って 『利益を独占する』 という意味がぴたりとはまる。
孟子は魯の宰相の世襲を 『壟断』 であると批判してこの例え話を持ち出した。お山の大将が利権を独占しそれを身内に引き継いでいく図は今も変わらない。世襲然り,天下り然りである。ただしその山は性善説を以てする孟子には必ず低いのである。
2009年01月08日
(い)衣食足りて礼節を知る
【倉廩實,則知禮節;衣食足,則知榮辱】出典管子(牧民)
原文は, 『倉廩満ちて礼節を知り、衣食足りて栄辱を知る。』 であり意味は, 『人は、物質的に不自由がなくなって、初めて礼儀に心を向ける余裕ができてくる。(Yahoo辞書大辞泉)』 である。
春秋時代,斉の桓公に仕えた宰相管仲が桓公を諫めた言葉である。管仲は, 「強兵の前に国を富ませること,それには先ず民生の安定と規律の徹底が必要である。」 と説き,桓公はその言を実践して春秋最初の覇者となった。
これは民側の心理として 『生理的あるいは安全の欲求が満たされなければ所属や愛の欲求を求めることはない。』(マズローの欲求段階説)が意味することと同じであろう。
2700年後の現在,雨露をしのぐことにも苦悩する民衆に向い 「目的意識」 を諭す為政者を管仲はこう言って嗤うだろう。 「臣は『総理』ではなく『不条理』である。先ずは字を習い書を読むべし。」
原文は, 『倉廩満ちて礼節を知り、衣食足りて栄辱を知る。』 であり意味は, 『人は、物質的に不自由がなくなって、初めて礼儀に心を向ける余裕ができてくる。(Yahoo辞書大辞泉)』 である。
春秋時代,斉の桓公に仕えた宰相管仲が桓公を諫めた言葉である。管仲は, 「強兵の前に国を富ませること,それには先ず民生の安定と規律の徹底が必要である。」 と説き,桓公はその言を実践して春秋最初の覇者となった。
これは民側の心理として 『生理的あるいは安全の欲求が満たされなければ所属や愛の欲求を求めることはない。』(マズローの欲求段階説)が意味することと同じであろう。
2700年後の現在,雨露をしのぐことにも苦悩する民衆に向い 「目的意識」 を諭す為政者を管仲はこう言って嗤うだろう。 「臣は『総理』ではなく『不条理』である。先ずは字を習い書を読むべし。」