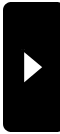2009年01月16日
(り)綸言(りんげん)汗の如し
「指導者の発言は『綸言汗の如し』であるべきだが,近頃は『失言汗の如し』だね」などと使う。
新明解故事ことわざ辞典によると,『綸言汗の如し』とは,『君主の言葉(=綸言)は,1度出た汗を再び体内にもどすことができないように,一度口から出たら訂正したり取り消したりすることはできないということ。いろはがるた(京都)の一。』となっている。君主の言葉を汗のようだとは出来の悪い言い回しである。
出典は漢書となっているが,実は漢書では『號令汗の如し』(出典1)とあり,その言葉は号令であって綸言ではない。そこで綸言について新字源で調べてみた。
綸(りん):①青色の帯ひも②いと,つり糸,弦楽器の糸,太い糸③天子の言葉④おさめる⑤したがう
綸言(りんげん):天子のおことば。天子のおさとし。出典礼緇衣
で,原文(出典2)では『王言は綸の如し』であり,
全文の訳は『王の言葉は糸のようなものであり,それが出るとき(発布の意味か)は綸のようになり,王の言葉が綸のようであれば,出るときは綍(ふつ:なわ)のようになる。』である。
つまり意味としては「王の言葉は糸(のような基本)であって,それが発布されるときは(撚り合わされ)太くなる(強くなって実用の増したものになる)。」が妥当である。
ふとくなることがひろがると捉えられ,「汗のようにひろがる」との類推につながり,「汗はもとにもどれない」との強引な結合によって,『綸言汗の如し』が作られたと考えてもおかしくはない。
何れにしても,端切れの寄せ集めを1本に綯(な)ったとしても,捻じるに捩じれて綱引きの具にもならないであろう。先ずは発言の一貫性を保つべきである。
出典1:【《易》曰“渙汗其大號”。言號令如汗,汗出而不反者也。】漢書楚元王傳
ここで易は【渙: 九五:渙汗其大號,渙王居,無咎。】周易易經
渙汗(かんかん):天子が詔勅や命令を出すこと。
あせが出ると全身に広がるように,天子の詔勅が広く民心にいきわたる意。
一説に,あせが出たらもとにもどらぬように,詔勅を一度出せば取り消せない意。
出典2:【王言如絲,其出如綸;王言如綸,其出如綍】禮記緇衣
新明解故事ことわざ辞典によると,『綸言汗の如し』とは,『君主の言葉(=綸言)は,1度出た汗を再び体内にもどすことができないように,一度口から出たら訂正したり取り消したりすることはできないということ。いろはがるた(京都)の一。』となっている。君主の言葉を汗のようだとは出来の悪い言い回しである。
出典は漢書となっているが,実は漢書では『號令汗の如し』(出典1)とあり,その言葉は号令であって綸言ではない。そこで綸言について新字源で調べてみた。
綸(りん):①青色の帯ひも②いと,つり糸,弦楽器の糸,太い糸③天子の言葉④おさめる⑤したがう
綸言(りんげん):天子のおことば。天子のおさとし。出典礼緇衣
で,原文(出典2)では『王言は綸の如し』であり,
全文の訳は『王の言葉は糸のようなものであり,それが出るとき(発布の意味か)は綸のようになり,王の言葉が綸のようであれば,出るときは綍(ふつ:なわ)のようになる。』である。
つまり意味としては「王の言葉は糸(のような基本)であって,それが発布されるときは(撚り合わされ)太くなる(強くなって実用の増したものになる)。」が妥当である。
ふとくなることがひろがると捉えられ,「汗のようにひろがる」との類推につながり,「汗はもとにもどれない」との強引な結合によって,『綸言汗の如し』が作られたと考えてもおかしくはない。
何れにしても,端切れの寄せ集めを1本に綯(な)ったとしても,捻じるに捩じれて綱引きの具にもならないであろう。先ずは発言の一貫性を保つべきである。
出典1:【《易》曰“渙汗其大號”。言號令如汗,汗出而不反者也。】漢書楚元王傳
ここで易は【渙: 九五:渙汗其大號,渙王居,無咎。】周易易經
渙汗(かんかん):天子が詔勅や命令を出すこと。
あせが出ると全身に広がるように,天子の詔勅が広く民心にいきわたる意。
一説に,あせが出たらもとにもどらぬように,詔勅を一度出せば取り消せない意。
出典2:【王言如絲,其出如綸;王言如綸,其出如綍】禮記緇衣
2009年01月15日
(ち)朝令暮改,魑魅魍魎,跳梁跋扈
「国会が朝令暮改を繰り返すなかで,霞ヶ関の魑魅魍魎はますます跳梁跋扈している」などと使う。
朝令暮改(ちょうれいぼかい):命令や法律が次々と変わって定まらないこと。朝に出した命令を夕方には改めるという意から。出典:漢書(新明解故事ことわざ辞典)
魑魅魍魎(ちみもうりょう):人々に害を加える化け物の総称。出典:春秋左氏伝(同)
跳梁(ちょうりょう):①おどり上がってはねまわる。②はびこって気ままにふるまう。(新字源)
跋扈(ばっこ):てごわくてわがままにふるまう。のさばる。横暴。(同)
朝令暮改と魑魅魍魎は,事例が多すぎて書ききれない。それより跳梁跋扈は故事成語でもおかしくないので,調べてみる。
それそれ新字源で分解すると,
跳:1.①おどる②おどらせる③はねる④とぶ⑤つまずく2.にげる
梁:①はし②はり③やな④つつみ⑤つよい⑥戦国時代の国名,魏が大梁に都を移してからの称(河南省開封県)
跋:①ふむ②あるく③はびこる④足を取られる⑤あとがき
扈:①夏の時代の国名,今の陝西省②春秋時代の地名,河南省にあった③したがう④おとも⑤とどめる⑥おおう⑦ひろい⑧はびこる
梁,扈を跳,跋のあとに続けるには必然性がない。だいたい,はりに上っておどるのは危険すぎるし,おともであるくのでは従順すぎる。わがまま,やりたい放題をイメージするのは無理がある。
ところが,梁,扈というどちらも河南省の地名であれば,その邑(ゆう:くに,むら)にまつわる出来事という可能性が考えられ,それが解れば故事成語になりそうだ。
余談
魑魅と魍魎は別モノらしい。見えない,見ずらいというのが特徴のようだ。新字源で分解してお祓いしておいた。
魑:离
魑魅:すだま,山林や沼沢の気から生じる人面鬼身の怪物
魅:みえない意①もののけ②みいる。人の心をひきつけ迷わす
魍:見がたい意
魍魎:山水・木石の精気から生じるという怪物。
魎:(新字源に説明なし)
鬼部で切り離すと
离:大きな口を開いたけものの形と山とから成り,山の神の意を表す。山の神霊,川の精霊。
未:もと,木に若い枝が出たさまにより,わかい意を表す。
罔:鳥獣をとらえるために張る「あみ」の意,借りて「ない」意に用いる。
兩:はかりのおもりの形にかたどる。「ふたつ」の意に用いる。
本来は「山と川で生まれる二つの見えない精霊」の一語であって,二語を並列したものではないかも知れない。
朝令暮改(ちょうれいぼかい):命令や法律が次々と変わって定まらないこと。朝に出した命令を夕方には改めるという意から。出典:漢書(新明解故事ことわざ辞典)
魑魅魍魎(ちみもうりょう):人々に害を加える化け物の総称。出典:春秋左氏伝(同)
跳梁(ちょうりょう):①おどり上がってはねまわる。②はびこって気ままにふるまう。(新字源)
跋扈(ばっこ):てごわくてわがままにふるまう。のさばる。横暴。(同)
朝令暮改と魑魅魍魎は,事例が多すぎて書ききれない。それより跳梁跋扈は故事成語でもおかしくないので,調べてみる。
それそれ新字源で分解すると,
跳:1.①おどる②おどらせる③はねる④とぶ⑤つまずく2.にげる
梁:①はし②はり③やな④つつみ⑤つよい⑥戦国時代の国名,魏が大梁に都を移してからの称(河南省開封県)
跋:①ふむ②あるく③はびこる④足を取られる⑤あとがき
扈:①夏の時代の国名,今の陝西省②春秋時代の地名,河南省にあった③したがう④おとも⑤とどめる⑥おおう⑦ひろい⑧はびこる
梁,扈を跳,跋のあとに続けるには必然性がない。だいたい,はりに上っておどるのは危険すぎるし,おともであるくのでは従順すぎる。わがまま,やりたい放題をイメージするのは無理がある。
ところが,梁,扈というどちらも河南省の地名であれば,その邑(ゆう:くに,むら)にまつわる出来事という可能性が考えられ,それが解れば故事成語になりそうだ。
余談
魑魅と魍魎は別モノらしい。見えない,見ずらいというのが特徴のようだ。新字源で分解してお祓いしておいた。
魑:离
魑魅:すだま,山林や沼沢の気から生じる人面鬼身の怪物
魅:みえない意①もののけ②みいる。人の心をひきつけ迷わす
魍:見がたい意
魍魎:山水・木石の精気から生じるという怪物。
魎:(新字源に説明なし)
鬼部で切り離すと
离:大きな口を開いたけものの形と山とから成り,山の神の意を表す。山の神霊,川の精霊。
未:もと,木に若い枝が出たさまにより,わかい意を表す。
罔:鳥獣をとらえるために張る「あみ」の意,借りて「ない」意に用いる。
兩:はかりのおもりの形にかたどる。「ふたつ」の意に用いる。
本来は「山と川で生まれる二つの見えない精霊」の一語であって,二語を並列したものではないかも知れない。
2009年01月14日
(と)東奔西走
「中小企業の経営者たちは資金繰りに東奔西走している」と用いる。
東奔西走の出典はよくわからないが,類義語の南船北馬の出典は以下だろう。
【...是以人不兼官,官不兼事,士農工商,鄉別州異...是以士無遺行,農無廢功,工無苦事,商無折貨,各安其性,不得相干...各有所宜,而人性齊矣。胡人便於馬,越人便於舟,異形殊類,易事而悖,失處而賤,得勢而貴。...】淮南子(齊俗訓)
...是を以て人は官を兼ねず,事は官を兼ねず,士農工商,鄉別に州異す。...是を以て士に遺行(いこう)無く,農に廢功(はいこう)無く,工に苦事(くじ)無く,商に折貨(せっか)無く,各其性に安んじ,相干(おかす)を得ず...各宜しき所有りて,人の性は齊(ひと)し。胡人は馬に便に,越人は舟に便になり,形を異し類を殊にするもの,事を易ふれば而ち悖(もと)り,處を失へば而ち賤しく,勢を得れば而ち貴し...
一人の者は二つの官職を兼ねることはせず,一つの官職は二つの仕事を兼ねることはせず,士農工商それぞれに区別があった。...こうして官吏には治務の遺漏なく,農民にはむだな骨折りなく,工人には困難な作業なく,商人には損失なく,各人が自分の持ち前に従って,互いに犯しあうことはなかった。...このように人にはそれぞれ長ずるところがあり,人の性に優劣はないのである。北方の異族は馬をのりこなし,南方の異族は船を乗りこなす。形や類のちがう者が仕事を替えれば失敗し,適所を間違えば賤しまれ,勢いに乗ずれば尊重される...
(参考:新釈漢文大系第55巻淮南子(中),明治書院)
資金繰りが厳しくなった理由には,貸し渋り・貸しはがしも売上低迷も放漫経営もあるとおもう。それを等しく救済するのはいかがなものか。似て非なるものを悪む俊士の治務に期待する。
東奔西走の出典はよくわからないが,類義語の南船北馬の出典は以下だろう。
【...是以人不兼官,官不兼事,士農工商,鄉別州異...是以士無遺行,農無廢功,工無苦事,商無折貨,各安其性,不得相干...各有所宜,而人性齊矣。胡人便於馬,越人便於舟,異形殊類,易事而悖,失處而賤,得勢而貴。...】淮南子(齊俗訓)
...是を以て人は官を兼ねず,事は官を兼ねず,士農工商,鄉別に州異す。...是を以て士に遺行(いこう)無く,農に廢功(はいこう)無く,工に苦事(くじ)無く,商に折貨(せっか)無く,各其性に安んじ,相干(おかす)を得ず...各宜しき所有りて,人の性は齊(ひと)し。胡人は馬に便に,越人は舟に便になり,形を異し類を殊にするもの,事を易ふれば而ち悖(もと)り,處を失へば而ち賤しく,勢を得れば而ち貴し...
一人の者は二つの官職を兼ねることはせず,一つの官職は二つの仕事を兼ねることはせず,士農工商それぞれに区別があった。...こうして官吏には治務の遺漏なく,農民にはむだな骨折りなく,工人には困難な作業なく,商人には損失なく,各人が自分の持ち前に従って,互いに犯しあうことはなかった。...このように人にはそれぞれ長ずるところがあり,人の性に優劣はないのである。北方の異族は馬をのりこなし,南方の異族は船を乗りこなす。形や類のちがう者が仕事を替えれば失敗し,適所を間違えば賤しまれ,勢いに乗ずれば尊重される...
(参考:新釈漢文大系第55巻淮南子(中),明治書院)
資金繰りが厳しくなった理由には,貸し渋り・貸しはがしも売上低迷も放漫経営もあるとおもう。それを等しく救済するのはいかがなものか。似て非なるものを悪む俊士の治務に期待する。
2009年01月13日
(へ)辟易する
「政治家連中の変わり身の早さと言い逃れの多さには辟易する。」などに使う。
この場合は『うんざりする』だか,広辞苑には『辟は避ける,易は変える意①驚き恐れて相手のために道を開いて立ち退くこと②勢いにおされてしりごみすること。』と有る。うんざりする のと 立ち退く のと しりごみする のが同じ言葉だとは妙である。調べてみた。
【..項王大呼馳下,漢軍皆披靡..項王瞋目而叱之,赤泉侯人馬倶驚,辟易數里..】出典:史記(項羽本紀)
..項王,大呼して馳(は)せ下り漢軍みな披靡(ひび)す..項王,瞋目(しんもく)して之を叱り,赤泉侯人馬倶(とも)に驚き,辟易すること数里..
披靡:道を開きなびく
瞋目:目をいからす
辟易:おどろきたじろぐ(新字源)
(四面楚歌の垓下を抜け出して追われ,ついに28騎となった項羽は数千の漢軍に囲まれたが,戦いに敗れるのではなく天に滅ぼされるのだと)項王が大声で馳せ下ると漢軍はいっせいに道を開き..項王が目をいからせて叱ると(迫ってきた)赤泉侯と馬は驚き,数里退いてたじろいだ。
春秋戦国時代の1里は300歩,1歩は6尺,1尺は10寸,1寸は2.25cmだから1里は405m
そもそも驚いてたじろぐと動けなくなるのではないか。それを何百mも逃げるとはどういうことか。さらに疑問は深まった。
項羽はそのあと顔見知りで昔の家臣であった呂馬童を見つけて「お前の手柄にせよ」と言って自ら首を刎ねた。その遺体を5人が取り合って手柄とし楊喜は赤泉侯に,呂馬童は中水侯などに封された。
以上はあくまで楚王項羽側の記述(項羽本紀)であり漢王劉邦(高祖本紀)側では【使騎將灌嬰追殺項羽東城,斬首八萬,遂略定楚地。】騎將灌嬰を使わし項羽を東城に追いて殺し,八萬を斬首し,遂に楚地を略定した。との記述があるだけである。
さて,辟易の意味は未だ曖昧であるが,「易きを辟けて(王位の略奪ではなく天命として)」項羽の自刎を促したとするのはどうであろうか?あるいは『三舎を避ける』の故事を引いて「易く数里を辟けて(旧恩に応える)」とするのはどうだろうか?(この場合数里はよほど短いので「恩知らず」の意味も含める。避から道(辶)がとれているところが意味深長である)
これであれば大軍で囲みながら,道をあけたことがすんなりと繋がるのだが。
余談
『三舎を避ける』は『晋の文王は流浪中に楚の成王に礼遇された際,もし戦うことになれば三舎を避けて返礼することを約束し,それを実行した。』という故事である。
舎は1日の行軍距離で30里(=12.15Km)
多勢に無勢の話だが,同様な話が三国志の張飛の長坂橋大喝にも出てくる。
この場合は『うんざりする』だか,広辞苑には『辟は避ける,易は変える意①驚き恐れて相手のために道を開いて立ち退くこと②勢いにおされてしりごみすること。』と有る。うんざりする のと 立ち退く のと しりごみする のが同じ言葉だとは妙である。調べてみた。
【..項王大呼馳下,漢軍皆披靡..項王瞋目而叱之,赤泉侯人馬倶驚,辟易數里..】出典:史記(項羽本紀)
..項王,大呼して馳(は)せ下り漢軍みな披靡(ひび)す..項王,瞋目(しんもく)して之を叱り,赤泉侯人馬倶(とも)に驚き,辟易すること数里..
披靡:道を開きなびく
瞋目:目をいからす
辟易:おどろきたじろぐ(新字源)
(四面楚歌の垓下を抜け出して追われ,ついに28騎となった項羽は数千の漢軍に囲まれたが,戦いに敗れるのではなく天に滅ぼされるのだと)項王が大声で馳せ下ると漢軍はいっせいに道を開き..項王が目をいからせて叱ると(迫ってきた)赤泉侯と馬は驚き,数里退いてたじろいだ。
春秋戦国時代の1里は300歩,1歩は6尺,1尺は10寸,1寸は2.25cmだから1里は405m
そもそも驚いてたじろぐと動けなくなるのではないか。それを何百mも逃げるとはどういうことか。さらに疑問は深まった。
項羽はそのあと顔見知りで昔の家臣であった呂馬童を見つけて「お前の手柄にせよ」と言って自ら首を刎ねた。その遺体を5人が取り合って手柄とし楊喜は赤泉侯に,呂馬童は中水侯などに封された。
以上はあくまで楚王項羽側の記述(項羽本紀)であり漢王劉邦(高祖本紀)側では【使騎將灌嬰追殺項羽東城,斬首八萬,遂略定楚地。】騎將灌嬰を使わし項羽を東城に追いて殺し,八萬を斬首し,遂に楚地を略定した。との記述があるだけである。
さて,辟易の意味は未だ曖昧であるが,「易きを辟けて(王位の略奪ではなく天命として)」項羽の自刎を促したとするのはどうであろうか?あるいは『三舎を避ける』の故事を引いて「易く数里を辟けて(旧恩に応える)」とするのはどうだろうか?(この場合数里はよほど短いので「恩知らず」の意味も含める。避から道(辶)がとれているところが意味深長である)
これであれば大軍で囲みながら,道をあけたことがすんなりと繋がるのだが。
余談
『三舎を避ける』は『晋の文王は流浪中に楚の成王に礼遇された際,もし戦うことになれば三舎を避けて返礼することを約束し,それを実行した。』という故事である。
舎は1日の行軍距離で30里(=12.15Km)
多勢に無勢の話だが,同様な話が三国志の張飛の長坂橋大喝にも出てくる。
2009年01月12日
(ほ)本末顚倒
【夫明王治國之政,使其商工游食之民少而名卑,以寡舎本務而趨末作者。】出典:韓非子(五蠹)
夫(そ)れ明王の治國の政は,其の商工游食の民をして少くして名(な)卑しからめ,以て本務を舎(す)てて末作に趨(はし)る者を寡(すくな)くす。
そもそも明君の国の治め方では,商人や工芸家など労働をせずに暮らす者をなるべく少数にし,かつ地位や名誉の低いものに扱い,そうやって人民の本務(耕作と戦闘)を捨てて末葉(商工)に走るものを減らすのである。
(参考:新釈漢文大系第12巻韓非子(下),明治書院)
韓非子は続けて,『ところが今の世では君主の近臣に取り持ってもらうことができるから,官爵を買うことができる。それができるから商人も工芸家も地位が卑しくない。無用の贅沢品や装飾物が市場でよく売れるからそれを扱う商人(や作る工芸家)は減りはしない。かれらの収入は農民のそれに数倍するから,農民や兵士を貴ばないのである。だから律儀な働き手が減って,商売人が増えるのである。』
--------------------------------------------------------------------------------------------------
商工業が労働をしないとはひどい言いがかりであるが,韓非子は農業と国防が根本,商工業が末葉として,国家の産業を樹木としてとらえているようだ。
枝葉が繁るのとは逆に根がだんだん痩せ細り最後は全体が倒れてしまうという恐ろしい予言である。
産業の現状を調べてみた。(下表)
平成19年度の国内総生産は515.8兆円で,そのうち農林水産業で7.4兆円(1.4%),卸売小売業は68.8兆円(13.3%),鉱・製造業は108.7兆円(21.2%),それ以外は韓非子の時代には,国家の事業として,あるいは民の労役として為されていたものばかりである。
農業の衰退には韓非子の嘆きが聞こえるようである。もし,食糧自給率を40%から80%に上げれば,今の倍の新しく248万人分の仕事が生まれる勘定である。
消費減速と自国通貨高によって,製造業が未曾有の危機となり,大規模な雇用調整もやむなしという風潮である。これも調べてみた。
産業関連表(内閣府統計局平成17年版)の中から”機械・電気・電子・情報・通信”の名のつくものを挙げてみると輸出は44.1兆円,輸入は21.3兆円差し引き22.8兆円の出超である。議論を簡単にするためこれをすべて失うと仮定すると製造業の生産は21.0%落ち込み244万人の雇用が失われることになる。
前述の農業であれば全員を吸収できる勘定であるが,もしそれを行わないとして他の産業での吸収を考えてみる。
下表にもどって,製造業の就業者1人当たりの生産額は情報通信業の2.1倍,サービス業の1.8倍,卸売・小売業の1.6倍,運輸業の1.3倍あるから,製造業が21%生産低下したとしても,これらの産業に移動するメリットはない。もし行えば国全体として生産性が低下する。
鉱業はあと2~3万人の吸収は可能であるが規模が小さい。公務は生産性からみれば十分吸収可能であるが,元が税金だから解決にはつながらない。緊急対応に限定すべきである。金融・保険には十分余力がある。エネルギーはあと100万人増やしても大丈夫である。不動産はなぜこれほど良好なのかわからないのでもう少し調べてから判断する。
販売・サービスへの移動はまさに本末転倒で,問題を複雑にし,回復を長引かせるだけである。製造業内で2割程度のワークシェアリングで耐えらるかどうかは検討の価値がある。100年に1度の危機であれば,緊急性を質にせず重要度の高いものから,百年の計を立てて臨むべきである。

夫(そ)れ明王の治國の政は,其の商工游食の民をして少くして名(な)卑しからめ,以て本務を舎(す)てて末作に趨(はし)る者を寡(すくな)くす。
そもそも明君の国の治め方では,商人や工芸家など労働をせずに暮らす者をなるべく少数にし,かつ地位や名誉の低いものに扱い,そうやって人民の本務(耕作と戦闘)を捨てて末葉(商工)に走るものを減らすのである。
(参考:新釈漢文大系第12巻韓非子(下),明治書院)
韓非子は続けて,『ところが今の世では君主の近臣に取り持ってもらうことができるから,官爵を買うことができる。それができるから商人も工芸家も地位が卑しくない。無用の贅沢品や装飾物が市場でよく売れるからそれを扱う商人(や作る工芸家)は減りはしない。かれらの収入は農民のそれに数倍するから,農民や兵士を貴ばないのである。だから律儀な働き手が減って,商売人が増えるのである。』
--------------------------------------------------------------------------------------------------
商工業が労働をしないとはひどい言いがかりであるが,韓非子は農業と国防が根本,商工業が末葉として,国家の産業を樹木としてとらえているようだ。
枝葉が繁るのとは逆に根がだんだん痩せ細り最後は全体が倒れてしまうという恐ろしい予言である。
産業の現状を調べてみた。(下表)
平成19年度の国内総生産は515.8兆円で,そのうち農林水産業で7.4兆円(1.4%),卸売小売業は68.8兆円(13.3%),鉱・製造業は108.7兆円(21.2%),それ以外は韓非子の時代には,国家の事業として,あるいは民の労役として為されていたものばかりである。
農業の衰退には韓非子の嘆きが聞こえるようである。もし,食糧自給率を40%から80%に上げれば,今の倍の新しく248万人分の仕事が生まれる勘定である。
消費減速と自国通貨高によって,製造業が未曾有の危機となり,大規模な雇用調整もやむなしという風潮である。これも調べてみた。
産業関連表(内閣府統計局平成17年版)の中から”機械・電気・電子・情報・通信”の名のつくものを挙げてみると輸出は44.1兆円,輸入は21.3兆円差し引き22.8兆円の出超である。議論を簡単にするためこれをすべて失うと仮定すると製造業の生産は21.0%落ち込み244万人の雇用が失われることになる。
前述の農業であれば全員を吸収できる勘定であるが,もしそれを行わないとして他の産業での吸収を考えてみる。
下表にもどって,製造業の就業者1人当たりの生産額は情報通信業の2.1倍,サービス業の1.8倍,卸売・小売業の1.6倍,運輸業の1.3倍あるから,製造業が21%生産低下したとしても,これらの産業に移動するメリットはない。もし行えば国全体として生産性が低下する。
鉱業はあと2~3万人の吸収は可能であるが規模が小さい。公務は生産性からみれば十分吸収可能であるが,元が税金だから解決にはつながらない。緊急対応に限定すべきである。金融・保険には十分余力がある。エネルギーはあと100万人増やしても大丈夫である。不動産はなぜこれほど良好なのかわからないのでもう少し調べてから判断する。
販売・サービスへの移動はまさに本末転倒で,問題を複雑にし,回復を長引かせるだけである。製造業内で2割程度のワークシェアリングで耐えらるかどうかは検討の価値がある。100年に1度の危機であれば,緊急性を質にせず重要度の高いものから,百年の計を立てて臨むべきである。